【Challenger’s Interview】廃漁具アップサイクルのamuがTRIBUSで得たつながりから編む新たなストーリー
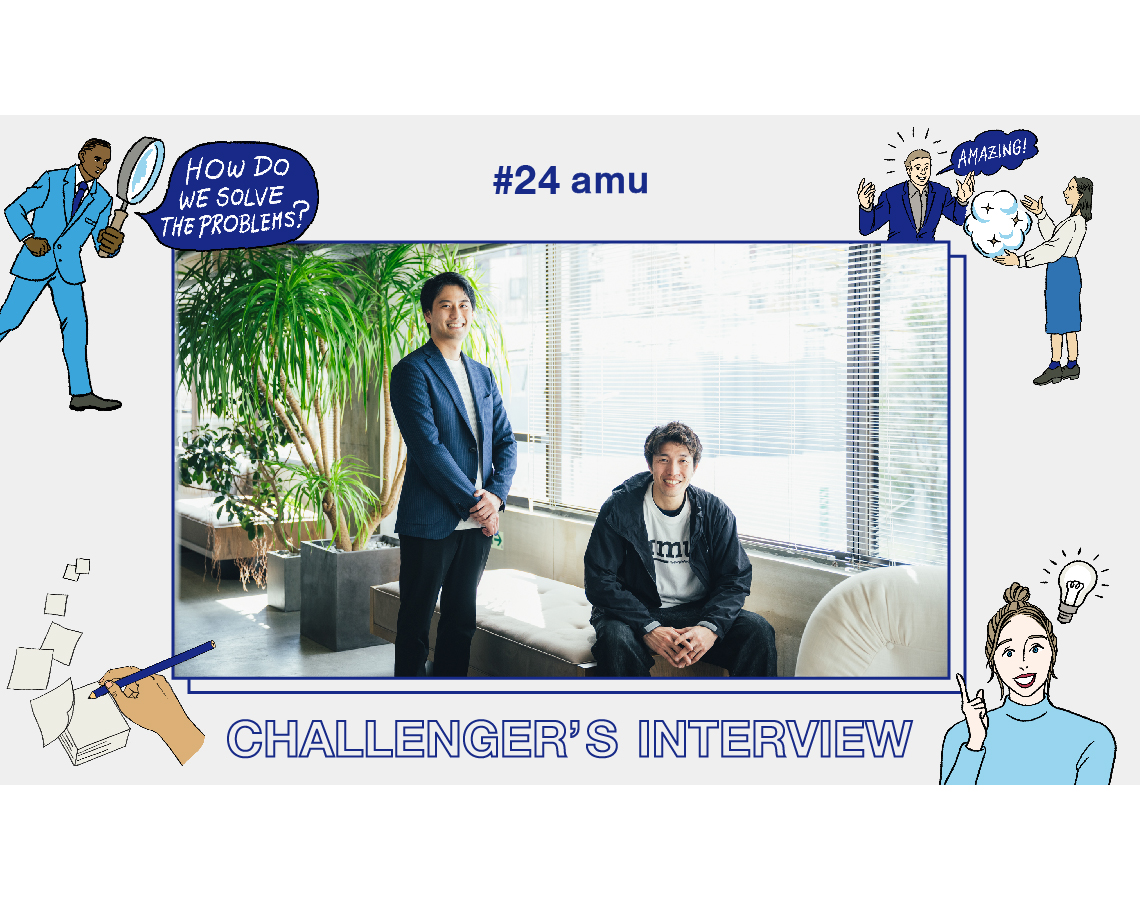
「TRIBUS2023」で2つの企業賞を受賞したamu。「いらないものはない世界をつくる」というビジョンのもと、廃漁具を回収し、新たな素材や製品として再生させるスタートアップだ。設立から2年未満ながら、自社ブランドを立ち上げ、協業や受賞歴も積み重ねるなど、勢いに乗る。今回は、amu株式会社で創業時から取締役を務める芦原昇平氏と、同社のカタリストを担当したエトリア株式会社 立石佐太郎に、TRIBUSアクセラレータープログラム期間中の活動内容と、そこから広がったそれぞれの可能性や今後の展望について伺った。
芦原 昇平
amu株式会社 取締役。2014年金沢大学地域創造学類卒。島根県海士町に移住し、空き家を改修した宿泊施設を新設するなど複数のプロジェクトの立ち上げに携わる。2019年宮城県気仙沼市に移住。気仙沼DMOマーケティングチームのリーダーを務める。同時に隠岐DMOの運営及びマーケティングチームのアドバイザーを兼務。2023年5月よりamu株式会社に参画。
amu株式会社:https://www.amu.co.jp/
立石 佐太郎
エトリア株式会社 所属。
2017年東北大学大学院工学研究科(修士)卒。新卒ではプラスチックメーカーの生産技術に従事。2020年に株式会社リコーに転職。2024年にエトリア株式会社(※)の設立に伴い、同社へ転籍。2023年に中小企業診断士に合格し、社外で経営支援の仕事も行っている。
※リコーと東芝テックの合弁会社
TRIBUS参画のきっかけは具体的な協業のイメージ
――まずはamuについて教えてください。
芦原 日本全国の漁港に眠る、捨てられてしまう漁具を回収してリサイクルし、製品化して世の中に届けるという事業を展開している会社です。回収からプロダクトをつくるところまで一気通貫で実施していて、プロダクトのブランドとして立ち上げた「amuca®」では、実際に廃漁具からつくった素材を販売しています。
 amu株式会社 取締役 芦原 昇平氏
amu株式会社 取締役 芦原 昇平氏
販売する素材は、回収した廃漁具からケミカルリサイクル(※1)によって高品質なナイロン6を生成し、ペレットや繊維、生地など希望にあわせて幅広いロットで提供する「amuca® NYLON6」と、マテリアルリサイクル(※2)によってペレットを生成する「amuca®︎ PA/PP/PE/PET」の、大きく二種類に分けられます。
今年の3月からは、Blueprint oneが運営するライフスタイルブランド「moment of OCEAN」とのコラボレーションにより、廃漁具由来のリサイクル素材である「amuca®︎ PA」をフレーム部分に使用したサングラスの販売を開始しました。この素材には、弊社の拠点でもある宮城県気仙沼市で回収したマグロ延縄漁の釣り糸が使われています。
※1 廃プラスチックを化学的に分解するなどして原料として再生する手法※2 廃プラスチックを溶解して原料として再生する手法
――設立間もない中、スピーディな展開ですね。
芦原 はい。実際に一般販売できるプロダクトをつくり出せたことに手応えを感じています。会社名のamuには「編集する」という意味が込められていて、これは各地域にあるストーリーを大切にしながら、新しい1ページをつくりたいという思いが込められています。私自身、何か地域の課題に取り組みたいと思って岩手県へ移住してきたので、今回のように実際に気仙沼の廃漁具を使った製品を形にして届けられたことを非常に嬉しく感じています。

――事業は順調そうですが、TRIBUS2023に応募したきっかけはどこにあったのでしょうか。
芦原 最初は弊社のお問い合わせフォームから、TRIBUSという取り組みがあることをご案内いただいたと記憶しています。TRIBUSとリコーさんについて調べていくなかで、リコーさんの製品に「樹脂判別ハンディセンサー」というものがあることを知りました。測定部に当てるだけでその場でプラスチックの素材が何かわかるということで、まさに自分たちが探し求めていた技術そのものだと思いました。
実は漁網にはさまざまなプラスチック素材が使われているんです。1種類ではなく、複数の種類の素材が混ざっている場合もあります。それが現場では判断できないので、これまではサンプルを採取して協業先に送り、分析をしてもらって、その結果を受けてどう対応するか検討する、というプロセスを踏んでいました。最大で90日間ほどかかることもあり、回収が難航する一因にもなっていました。それが現場で即時に分析できるとなると、事業のスピードが一変するわけです。この製品を通じてリコーさんと協業する明確なイメージが持てたこともあり、TRIBUSへの応募を決めました。

――リコー社員としてamuのTRIBUSプログラム期間の活動をサポートしたカタリストの立石さんは、amuのどのようなところに魅力や可能性を感じましたか。
立石 まずamuさんのピッチを聞いて衝撃を受けた点が、日本の海岸に漂着している海洋プラスチックごみのうち、漁業関連ごみが質量ベースで4割強を占めている(※)ということでした。海洋プラスチック問題というものは認識していたのですが、漁業と関連しているということは知りませんでした。海鮮料理が好きなので、自分にもその責任の一端があるとも感じましたね。
※出典:平成30年9月 環境省「海洋ごみをめぐる最近の動向」
 エトリア株式会社 立石 佐太郎
エトリア株式会社 立石 佐太郎
加えて、前職がプラスチックのメーカーでしたので、リサイクル自体をどのように行っているのかという点も気になりました。というのも、プラスチックは不純物を嫌う素材なんです。漁具・漁網と聞いたとき、不純物がたくさん付着しているだろうから再生も難しいのではないか、と直感的に思ったのと同時に、それをどうやって事業として成り立たせ、価値を生み出しているのかに非常に興味が湧いて、amuさんの伴走支援を希望しました。
リコーのネットワークを活かした「つながり」の提供
――具体的には、どのように伴走支援されたのでしょうか
立石 amuさんの場合は、最初のピッチでも「樹脂判別ハンディセンサー」への期待を明確に言及されていたので、まずその使用機会を設けるという明確なミッションがありました。一方で、それだけでは想定の範囲内になってしまうので、リサイクルの入口や出口で何かリコーのアセットを活用できないかと考えました。定例のミーティングを通してamuさんへの理解を深めながら、課題もヒアリングさせていただき、社内のツテをたどって何かよいアプローチはないか探してみるところから始めました。
最初は出口の部分で、リコーの複合機にamuさんのリサイクル素材を使えないかと考え、資材調達部門や再生樹脂開発グループなどに相談しました。しかし、ナイロン6は複合機の素材としての使用量は少なく、新たに導入するのは現実的ではないとわかりました。
では入口で何かできないかを考えたときに、リコーには全国の拠点からSDGsキーパーソン(※)が集まるコミュニティがあることに思い当たったんです。運営の方に相談してコミュニティに参加させてもらい、地元の漁港などamuさんの事業に関連しそうな方々を紹介してほしいと呼びかけました。すると、各エリアの営業の方々から「協力したい!」という反応をいただき、漁港の紹介だけでなく、事業への提案も数多く寄せられました。
※リコーが2018年からスタートさせた制度。年度の始めに登録を募り、毎月実施している研修において、最新の社会動向やリコーグループの取り組み、支社の好事例を共有し、SDGsへの取り組みをレベルアップさせている。

芦原 amuの活動では日本全国のどこにどんな漁網があるのか把握して回収するだけでなく、それらの出口も同時に考える必要があるんです。それをまずリコーさんのネットワークを通じて探していただき、つないでいただく。特にこうした点で、立石さんには非常にお世話になりました。
実際に立石さんの勤務地でもある沼津の漁港で漁網を回収させていただき、ハンディセンサーで分析、リコーさん側で詳細な分析をしていただくことで、その精度がどれくらい高いのかを検証していただきました。
――当初の想定を超えるかたちで、ハンディセンサーでの分析を実現されたのですね。何か難しい場面はありましたか。
立石 やはりスタートアップと大企業との取り組みですから、スピード感・価値観のギャップを感じる場面というのはありましたね。たとえば技術部門から私宛に届く指摘はすべてごもっともで、正確性を追求すべきであるというプロフェッショナルな考え方には共感しましたが、amuさんの求めるスピード感を考えると、できるだけ早く次のステップへ進めたいと思うような場面もありました。カタリストとして、両者の立場を尊重しながらコミュニケーションを進めることを意識していました。

芦原 基本的に立石さんが調整してくださっていたので、あまり難しさは感じませんでしたね。冒頭で立石さんもおっしゃっていたように、プラスチック素材のリサイクルは難易度が高いんです。だからこそ技術職の方々は正確性を追求しようとする。その視点や考え方に対する理解は、以前より深まったと感じています。
立石 そうした捉え方は非常に重要だと思います。スタートアップと大企業という異なる文化が交わるとき、大切なのは相手を理解しようとする姿勢だということを、この経験から改めて学びました。意見の違いに直面したときに、「こういう考え方もあるんだ」とまず受け止めることが、カタリストとして非常に大事なことだと考えています。
TRIBUSをきっかけに始まる新たなストーリー
――TRIBUSで得られた思いがけない成果があれば、教えてください。
芦原 最初はハンディセンサーという技術を非常に魅力的に感じて参画を決めたわけですが、地域の方や企業さんとのつながりまで提供していただき、ここまで支援してくださるのかと驚きました。実際にご一緒して実感したのは、リコーさんの「幅の広さ」です。全国各地に拠点があり、かつ事業領域が広いからこそ、さまざまなつながりを提供していただける。いちスタートアップでは得られないようなつながりを引っ張ってきていただけたのは、とてもありがたかったです。

実際に岡山支社の方からは地元の企業を複数ご紹介いただきました。皆さん快く応援してくださり、そのご縁は今でも続いています。地元企業の方々と話すなかで、岡山の廃漁網を岡山のリサイクル会社でリサイクルして、その素材を岡山で活用するという、地域内で素材を地産地消するようなアイデアも生まれています。輸送にかかる費用面・環境面のコストが抑えられることに加え、地元のストーリーづくりにも貢献できる。こんなサイクルをつくれたら素敵だなと思っています。
――立石さんには変化はありましたか。
立石 もともと私自身、TRIBUSには社内起業家として何度か応募していたこともあり、新規事業に対する理解は深いほうだと思っていました。ですが、amuさんの伴走を通じて実感したのは、新規事業にはアイデアやビジョンだけではなく、柔軟な対応力や行動力が必要だということです。
具体例で言うと、ハンディセンサーでは「ナイロン」という判別がされた素材でも、実際にはケミカルリサイクルに回せない「共重合」で合成されているケースがあると途中で判明しました。もともとケミカルリサイクルを前提に進めていたので、その前提条件が覆ってしまいどうするのだろうかと思いましたが、amuさん側で議論されて、なんとかマテリアルリサイクルで活路を見出されたのです。この対応力には驚かされました。

芦原 確かにあの時は難しい状況ではありました。しかし、ケミカルリサイクルができないとわかったので、シンプルに考えて、別のものをつくるしかない。そこでペレットというチップ状の原料にすることで活用できないかと、各所に相談しながら試験を繰り返しました。そのなかで唯一「これであれば活用できそうだ」というアイデアが出てきて、現在はリサイクル実現に向けた最終段階に入っています。とにかく出口がないかと探し回りました。
立石 まさに行動力ですね。以前、気仙沼にうかがったときにamu代表の加藤さんがお話されていたのですが、「人にはいろいろな色の『火』が灯っている。その色が混ざることで生まれる新しい色の『炎』が生まれる。だから、『火』を持っていそうな人を見つけたら遠くであってもまずは足を運んで会いに行く。そうすると、思いがけないアイデアが生まれるんです。」とおっしゃっていました。それはすごく素敵な考え方だと思って、私も会いたいと思った人にはなるべく足を運んで会いに行くことを心がけるようになりました。
――TRIBUSでさらなる輪が広がっているとうかがいました。
立石 TRIBUS2024の参画企業のなかにa.s.istさんという会社がいらっしゃるのですが、「樹脂判別ハンディセンサー」の判別可能数を1種類から2種類に増やしたと成果報告をされていて。これは漁網判別の効率化につながるのではないかと考え、すぐにamuさんにご紹介しました。
芦原 立石さんがカタリストとして担当されていたCircloopさんもご紹介いただきましたね。リユーザブルカップシェアリングサービスを展開されている企業さんですが、石油由来の素材が使えないかというご相談をいただき、実現に向けて話を進めている最中です。
TRIBUSに今後どのような企業さんが参画されるのか、とても興味があります。立石さんのようにamuを思い出してつないでくださることもありがたいですし、逆にamuが採択企業さんの力になれることもあるかもしれません。TRIBUSを起点に、また新しい可能性が広がっていくような気がしていて、とても楽しみです。

PHOTOGRAPHS BY TADA (YUKAI) TEXT BY MARIE SUZUKI
