【Challenger’s Interview】研究を社会に生かす挑戦。東大発a.s.istがもたらす現場の変革
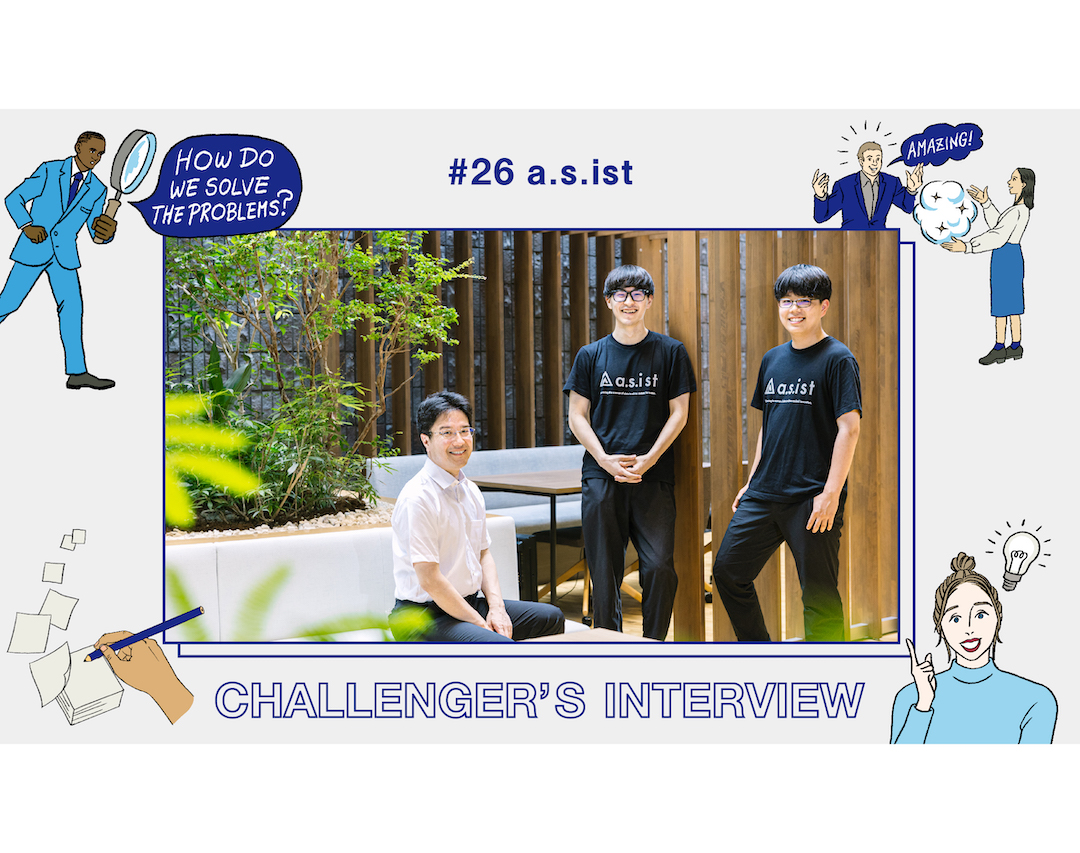
「TRIBUS2024」で審査員賞特別賞を受賞したa.s.ist(アシスト)。東京大学のメンバーで構成される同社は、材料開発や物性実験のデータに対してベイズ推論やスパースモデリングといったデータ解析技術を活用し、ソリューションを提供している。事業内容は難解だが「研究を社会に応用してみたい」と話す同社社長の林悠偉氏とCTO森口椋太氏の思いはいたって純粋で素朴だ。その“応用”は企業や社会に何をもたらしうるのか。「樹脂判別ハンディセンサーの混合物判定アルゴリズムの進化」で協働したリコーデジタルサービスの釜谷智彦とa.s.istの林氏、森口氏に話を聞いた。
林 悠偉
株式会社a.s.ist 代表取締役CEO。東京大学大学院新領域創成科学研究科。大学院ではX線・中性子散乱におけるベイズ推論の研究を行う。国内スタートアップにて機械学習の研究開発に従事した後、現職。JST BOOST NAISプロジェクト生。
森口 椋太
株式会社a.s.ist 代表取締役CTO。東京大学大学院理学系研究科。 大学院ではメスバウアー分光におけるベイズ推論の研究を行う。国内スタートアップにて機械学習の研究開発に従事し、開発に携わったシステムで特許取得。未踏2023年度スーパークリエイター
釜谷 智彦
リコーデジタルサービス BU環境・エネルギー事業センター所長
学術研究を応用し現場の“光”に変える
――あらためて、a.s.istの事業内容について教えてください。
林 私たちは、統計的AI技術を使ったデータ解析ソリューションを提供しています。もともとは東京大学の研究室で、ベイズ推論というアルゴリズムを研究していたメンバーで立ち上げた会社です。一般的に使われている深層学習型のAIは高い精度で予測や分類ができる一方で、「なぜその結果が出たのか」という根拠を人間が理解するのは難しいという課題があります。私たちの手法は、そうした「ブラックボックス」型のAIとは異なり、結果の根拠や背景を説明できる「解釈性」を重視しているのが特徴で、解析した結果はすべて数式などで説明できます。
 株式会社a.s.ist 代表取締役CEO 林 悠偉氏
株式会社a.s.ist 代表取締役CEO 林 悠偉氏
会社を立ち上げた当初は、生成AIを使ったシステムの受託開発をしていましたが、事業を進めるうちに「自分たちにしかできないことをやりたい」と思い直し、方向転換しました。今のような研究開発型の事業になったのは、起業して半年ほど経ってからです。最初は不安もありましたが、自分たちの研究した技術の可能性を試したいという気持ちが強かったですね。
森口 ベイズ推論は、実は日本が強い分野なのですが、産業界で応用されているケースは海外も含めてほとんどありません。企業での実装例が少ないからこそ、長年研究してきた私たちが応用していく意味があると考えましたし、何より、自分たちの研究が応用できるものなのかを知りたかった。事業として成立するかは正直自信がなかったのですが、純粋に知りたい、試したいという気持ちが強かったです。
 株式会社a.s.ist 代表取締役CTO 森口 椋太氏
株式会社a.s.ist 代表取締役CTO 森口 椋太氏
――実際に企業からの反応はどうでしたか?
林 私は森口とは違って自信があったのですが(笑)、それでも思った以上にニーズはあるという印象です。とくに、複雑なデータを扱う製造業の方々からは「ずっと課題だったテーマに光が見えた」と喜ばれることもあります。
当初は主に材料開発分野に貢献することを想定していたのですが、実際には製造ラインの現場からのニーズも多くありました。製造ラインはデータにノイズが入りやすい環境になりがちで、大量のデータが取得されても、扱い方がわからず放置されていたり、限定的あるいは属人的な解析にとどまっていたりするケースがあります。そこで、私たちが必要なデータだけを抽出し、自動で解析結果を可視化する方法をご提案する。こうした現場に貢献できるということ自体が、私たちにとっても新しい発見でした。
 リコーデジタルサービス BU環境・エネルギー事業センター所長 釜谷 智彦
リコーデジタルサービス BU環境・エネルギー事業センター所長 釜谷 智彦
釜谷 データに含まれるノイズを除去して真の情報を取り出すというのは、まさにリコーも苦戦してきた部分です。a.s.istさんの技術は、いわば海辺で風の音にかき消された声をクリアに拾うようなもの。現場で活きる力があると感じました。
4カ月という制約から見出された道筋
――TRIBUSに参加したきっかけは?
森口 ご一緒できる企業をWebで探しているなかでTRIBUSを知り、そこからリコーさんについて調べていくうちに、樹脂判別ハンディセンサーの存在を知りました。普通、計測器って大型で、持ち運ぶなんて不可能なんですよ。そんななかで、こんなに小型でスペクトル解析(※)ができる製品があると知って、興味を持ったのがきっかけです。
※物質に含まれる成分や性質を、光や電磁波の波長ごとの反応を分析して調べる手法。
林 私たちのデータ解析のソリューションは、それまではソフトウェア単体での提供にとどまっていました。事業を進めるうちに、やはりハードウェアと組み合わせることで提供価値をさらに広げられるのではないかと考えるようになっていました。その可能性を模索していたところ、樹脂判別ハンディセンサーを貸与していただける可能性があることがわかり、TRIBUSへの参加を決めました。

――どのようにプロジェクトは始まったのでしょうか?
釜谷 もともとハンディセンサーは、プラスチックのリサイクル工程で使うことを想定して開発した製品でした。ただ、実際に世に出してみると、循環型社会における“動脈”(※)である製造の現場でも活用されるようになりました。まずは知ってもらい、活用できる場面を広げる。そして、場面に応じて機能を追加・改善し、より循環型経済に貢献できる製品にしていきたい。そうした考えのもと、これをアセットとして提供し、新たなアイデアを募ることをTRIBUSのテーマにしたのです。
※循環型社会における「動脈」は製造・供給側、「静脈」は廃棄物回収・リサイクル側を指す。
林 まさに私たちが取り組みたいテーマそのものでした。当社の技術にも興味を持っていただき無事に採択されたのですが、正直なところ、最初は手探りでした。スペクトル解析の分野で貢献できるとは思っていたものの、具体的にどこまで貢献できるのか、どう価値に繋がるのかは未知数、という状態からのスタートでした。

釜谷 TRIBUSでは、最終のピッチまで4カ月という期間が設定されているので、この期間から逆算して何を成果として発表できるかを考える必要があります。その点は、私のチームがリードした部分でした。
樹脂は、単一素材か混合物かを判別するのが非常に難しい。単一だと思ってリサイクルに進めていた素材が、途中で混合物だったと判明することもあります。そうなると、リサイクル工程全体のコストも期間も大きく変わってしまいます。場合によってはリサイクル自体を諦めざるを得ないこともある。だからこそ、初手の段階で確実に混合物を判別できるようにすることは、現場にとって大きな意味を持ちます。そうした背景から、a.s.istさんには、初手での混合物判定精度の向上というテーマを提案しました。
森口 この提案は非常にありがたかったです。開発の方向性が明確になり、プロジェクトが一気に動き出したのを覚えています。TRIBUSでは、ただ自分たちで考えるだけではなく、リコーの社員さんが本気で寄り添って伴走してくれるのだと、身をもって実感しました。

TRIBUSがもたらした希少な出会い
――TRIBUSを通じた成果について教えてください。
林 「樹脂判別ハンディセンサーの混合物判定アルゴリズムの進化」が今回の成果物です。従来は熟練者でなければ判断できなかった混合物の有無と樹脂成分の数を、計測データから自動で判別できるようになりました。ハンディセンサーでは単一か混合か、測定前に人が判断して手動でモードを切り替える必要がありましたが、その切り替えも自動化することで、初手の段階で確実な解析につなげられるようになりました。
森口 当社にとっては、自社技術を外に向けて実例として語れるようになったという点でも大きな成果です。これまでお仕事をさせていただいた事例は、ソフトウェアのデータ解析がほとんどで、機密性が高く、説明の際にお見せできるものがありませんでした。リコーさんには展示会でもハンディセンサーをお貸しいただくなど、具体的な事例として紹介をさせていただいています。技術が理解していただきやすいので、とてもありがたいです。

――TRIBUSに参加して、どんな気づきがありましたか?
林 本当にゼロの状態から丁寧に一歩ずつ積み上げるような4カ月でした。ハードとソフトの融合において、最初の一歩・二歩をしっかり踏み出せたのは、TRIBUSのプログラムと伴走してくださったリコーの皆さんのおかげだと感じています。
森口 気づきというより感想になってしまいますが、樹脂判別センサーを貸与していただいた際、会社のメンバーで実際に机や椅子など身近な素材を判別してみたんです。すると、きちんと近赤外スペクトルのデータが表示される。軽量で持ち運べる上に、高度なデータがすぐに取れるというのは、驚きでした。メンバーからも「すごい!」と声が上がりました。環境によっては取得が難しいデータが簡単に取れるリコーさんの技術に純粋に驚きましたし、開発のモチベーションも上がった瞬間でした。
釜谷 それは嬉しい感想です。実は、a.s.istさんのように基礎研究を重視してしっかり取り組んでいる企業と出会う機会は、これまではあまりありませんでした。産官学連携で大学や研究機関と組むことは多いですし、スタートアップとの出会いもありますが、多くはすでに事業を確立している企業です。こうしたベースの技術を研究している、いわゆるシード段階にあるスタートアップと繋がるという発想自体がなかったというのが本音です。ベイズ推論自体は昔からある推論方法ですが、それを今も研究し、さらに応用しようとしているプレイヤーがいるなんて思いもよらなかった。こうした意外な出会いがあるのは、まさにオープンイノベーションならではだと思います。

a.s.istさんと話すなかで、あらためて気づかされたのは「理論に立ち返る」ことの重要性です。事業のなかでは、どうしても製品の機能を取捨選択しなければならない場面があります。それを単に諦めるのか、理論をきちんと理解したうえで選択をするのか、という両者には大きな差があるわけです。ベースの理論をきちんと理解し、結果の説明ができる状態にしておく。そうした原点に立ち返る必要性をチームメンバーに思い出してもらうきっかけになったと思います。
――今後に向けた展望は?
林 今回の取り組みはまだ実装して世に出す段階には至っていませんが、どのように製品化していくかについて、リコーさんへの具体的に提案を進めているところです。私たちのアルゴリズムの精度を評価していただき、リコーさんの求めるレベルまで引き上げる必要があると考えています。最終的には世に出してこそ、この技術の価値が証明されると思っていますので、実装まで進めていきたいですね。
釜谷 a.s.istさんとは逆に、私たちは「ハードからソフトへ」、つまりデータをどう活用するかをもっと考えることが、クライアントへの価値提供につながるのではないかと思っています。もちろん、樹脂判別ハンディセンサー自体も今後さらに進化させていきたいです。小型化させて、スマートフォンと連動できるようにするとか。まだまだチャレンジできることは多いです。私たちにない発想や技術でアイデアをいただきながら、これからも循環型社会の形成に貢献していきたいですし、TRIBUSでの出会いにもこれからも期待したいです。

PHOTOGRAPHS BY AKIKO SUGIYAMA TEXT BY MARIE SUZUKI
