TRIBUSで得たかけがえのない経験・知見を活かしそれぞれのネクストステージへ。TRIBUS社内起業家1期生「卒業式」レポート

TRIBUS(トライバス)は社内外からイノベーターを募り、リコーのリソースを活用しイノベーションにつなげるプロジェクト。ワークプレイスやイメージング領域にとどまらず、社会の広い分野での課題解決を目指します。この度、社内起業家1期生が4年間のTRIBUSでの活動を経て卒業を迎えました。卒業式では活動報告と事業の今後の展開などを発表しました。
卒業を迎えたチームとリーダー
【StareReapチーム】野村敏宏・林達之
産業印刷技術からスピンアウトした特殊な2.5D印刷で、アートブランドの構築を目指す。
【image pointerチーム】高橋朋子
手持ちで使える小型プロジェクター RICOH Image Pointer GP01を開発し、販売を行う。
【WEeeT-CAMチーム】斎藤啓
3Dプリント技術を活用し、途上国におけるピコ水力発電事業の開発に取り組む。LIFE PARTSブランドとして、3Dプリンターの材料販売等複数の事業を展開。
【RANGORIEチーム】綿石早希
インド柄のアクティブウェアの製造販売を通し、女性のエンパワーメント、インドの農村部に住む女性の雇用創出を目指す。
【RxRチーム】前鼻毅
VRが一般化した社会での快適で便利な働き方実現を目指す。
開会の挨拶は、2019年度プログラム運営キャプテンの小笠原氏が務めました。

発足当時、社員からの発案で既存のルールに縛られない新しい挑戦の場を求める声が上がり、現在のプログラムが立ち上がった経緯などを説明。卒業を迎えるチームに対し、自分で考え、自分で決める、その不安が財産になるというメッセージを込めてプログラムを募集したことを踏まえ、それぞれの目線からストーリーを語ってほしいとの言葉で挨拶を締めくくりました。
1.StareReap
野村敏宏

2.5D印刷の技術でアート業界にチャレンジし、国内外のアーティストと多数コラボレーションを実現。現代アート業界で好評を博し、400作品、1,930点のアート作品を販売しました。
当日の発表ではリーダーの野村敏宏氏が某バラエティー番組風にユーモアを交えながら、チームの成功と失敗を発表しました。チームメンバーはリーダー野村氏の他、デザイン出身の林氏、インク技術者の志村氏、販売の小林です。「非常に苦しい中、楽しみながら取り組んできました」と野村氏は語りました。
プロジェクトのきっかけはリコーの技術が起点だったとのこと。複製画が原画の価値を超えることがない、という現状を目の当たりにした時、チームメンバーの林氏が現代アートに目を付けたことで、事業としての道が開かれました。様々な技術を駆使し、繊細な表現や立体的な表現が可能になった結果、国内外のアーティスト、総勢70名ほどと共創、400作品を世の中に打ち出す結果になりました。
発表の中で野村氏は「実はアーティストの一番の存在意義というのは、歴史に名を残すことです。その結果として、美術館などに作品を寄贈することを1つの目標にしています。手前味噌ですが、その意味で我々は美術館に所蔵されるまでの成果創出に至っています。」と自信を持って発表しました。
プロジェクトは2021年に黒字を達成。その後、事業環境を精査した結果、活動中止の判断に至ったものの、2022年には「令和4年度文化庁長官表彰」にも選出されるなど高い評価を得ました。
事業の成功には軌道修正が大切であると語る野村氏。後続チームに向けた教訓として、事業は有限であること、優先順位を決めること、そして今後活動するチームのリーダーにはフレキシブルに対応できるようなマインドや強いリーダーシップを期待すると締めくくりました。
2.Image Pointer
高橋朋子

手持ちで使える小型プロジェクター RICOH Image Pointer GP01を開発・販売。 クラウドファンディングでは調達額No.1※1や大学文教販売数No.1※2を達成しました。現在製造分をもって販売は終了予定とし、卒業を迎えました。
※1)2020年クラウドファンディングサイトKibidango, GREEN FUNDINGのプロジェクタカテゴリにおいて※2)2022年1~3月大学生協でのプロジェクタカテゴリの販売数実績において
当日はリーダーの高橋朋子氏がポケットに入るサイズで手に持って使えるという特徴を持ったimage Pointerの販売経験について発表を行いました。
冒頭、「事業を作ることは楽しい、顧客と商品を作ることもとっても面白いということをお伝えしたいと思います。もちろん苦労もたくさんありましたが、せっかく自分たちでやりたいと言ってやっているものなので。」と社内起業の魅力を語りました。
オンラインの場合、画像共有、動画共有は簡単にできますが、リアルの方が難しいという課題に目を付け、レーザー型のハンディープロジェクターで解決しようというのが最初の想いで、開発に至ったといいます。
新しいものを提案した際、一期生ということもありどれだけの人がお金を払ってくれるのかという疑問が社内で上がったそうです。その課題を突破するためクラウドファンディングを行った結果、調達額は目標額1,000万円を大きく超え、3,400万円を超える着地となり発売が決定しました。
最後に高橋氏は「自分で判断して進めたことによって、儲かる、儲からない、全然ダメだったというのが明らかにすべてお金で響いてきますので、その辺りがとても楽しい経験でした。」と語りました。
3.WEeeT-CAM
斎藤啓

再生プラスチックを利用して3Dプリンターで成形した羽を用いた装置を使い、少ない水力で発電可能な「ピコ水力発電システム」。新興国の電力不足問題に挑んできました。ビジネス開拓と技術開発にイチから挑み、順調に顧客を獲得していきました。Good design賞や国交省採択プロジェクト、JICAの「中小企業・SDGsビジネス支援事業」に採択されるなど国内外問わず評価されてきました。卒業式では、今後も活動を続けて行く旨を発表しました。
発表の中でリーダーの斎藤啓氏は「私はもともと日本やアメリカ、欧州で3Dプリンターの材料開発や研究、将来構想企画などを担っておりましたが、若干日本が遅れているという焦りから、日本から発案してできるビジネスモデルを作れないかと考えて提案したのがこのテーマです。」と起業を決意したきっかけについて語りました。
プロジェクトは白紙に近い状態で開始。ビジネス開発と技術開発、両方ともイチから立ち上げなければいけない非常にチャレンジングなテーマだったとのこと。しかし、トライアル期間中、コロナをきっかけに、アジアを拠点に考えていたところを国内にシフトしながらも顧客を獲得し、現在でも国内外から多くの問い合わせがきています。
ビジネス面での成功のみならず、技術開発についても、3Dプリンターでの水力発電に実用レベルで使える耐水化技術と金属並み樹脂金属化技術を開発。国際特許を取得しました。また、社内評価としても革新技術賞を受賞しました。
その後は事業拡大のためオープンイノベーションを実施。水車一筋32年のシーベル株式会社と連携することとなりました。
シーベル株式会社は下水道に着目していましたが、小水力発電では錆びてしまうという課題がありました。そこで3Dプリンター水車を製作する提案を行い国交省に提案したところ、採用となりました。
発表の最後には、JICAのプロジェクトに採択されたことも発表し、引き続きチャレンジを続けていくと締めくくりました。
4.RANGORIE
綿石早希

インド農村部の女性の雇用創出を目的としたエシカルなアパレルブランド「RANGORIE」。インドの都市をモチーフとした個性的な柄や着心地の良さから話題を集めました。コロナ禍にブランドを開始したこともあり、苦労もありましたが全部で5つのコレクションを発表しました。卒業式当日はファッションショーを開催。卒業式では今後の展開として合同会社For DiLへの事業譲渡を発表しました。
リコー内で初のアパレルにチャレンジしたリーダーの綿石早希氏は発表の冒頭「一人一人が可能性を最大限に発揮できる社会をつくるということをミッションに掲げて、インドの農村部で女性たちと一緒にインドの柄をあしらったヨガウェアや下着を事業として展開してきました。」と事業のミッションを語りました。
そこから舞台は暗転。アパレルらしくファッションショー形式で過去のコレクションについて発表を行い、会場は驚きに包まれました。モデルはそれぞれインドの各都市にインスパイアされたウェアに身を包み登場しました。
当日はチームが設立に携わった工房の様子も紹介されました。現在は総勢9名の女性たちが働いているこちらの工房は、現地の協力NGOであるDrishteeに協力を仰ぎ募集を行い、手を挙げた現地の女性たちと一緒に作りました。
「一人一人が可能性を最大限に発揮できる社会をつくる」がミッションのランゴリーは、金銭だけの提供では現地の女性のためにならないと考え、工房を自分たちで運営していく意識をもってもらうため、工房で働く女性にマイクロファイナンスという形でローンを組んでいただき、初期費用を賄いました。その後工房の立ち上げにランゴリーメンバーがインドへ出向き、品質や工房内でのあり方などの教育を行い、工房で製造受注ができるようになりました。この方法はのちにDrishtee+現地の女性グループ+支援会社という3社での共創におけるモデルケースにもなりました。
現在、RANGORIEは合同会社ForDiLに譲渡されています。譲渡先について綿石氏は「日印のどちらにもバックグラウンドを持っているForDiL様に、事業およびブランドの譲渡をすることに決定しました。代表の方が日印ハーフの方で、ご自身のルーツがインドにあり、日本ではアパレル事業、メンタルケア事業を展開していらっしゃる会社さんです。」と愛するブランドを託すにふさわしい企業に譲渡できたと語りました。
5.RxR
前鼻毅
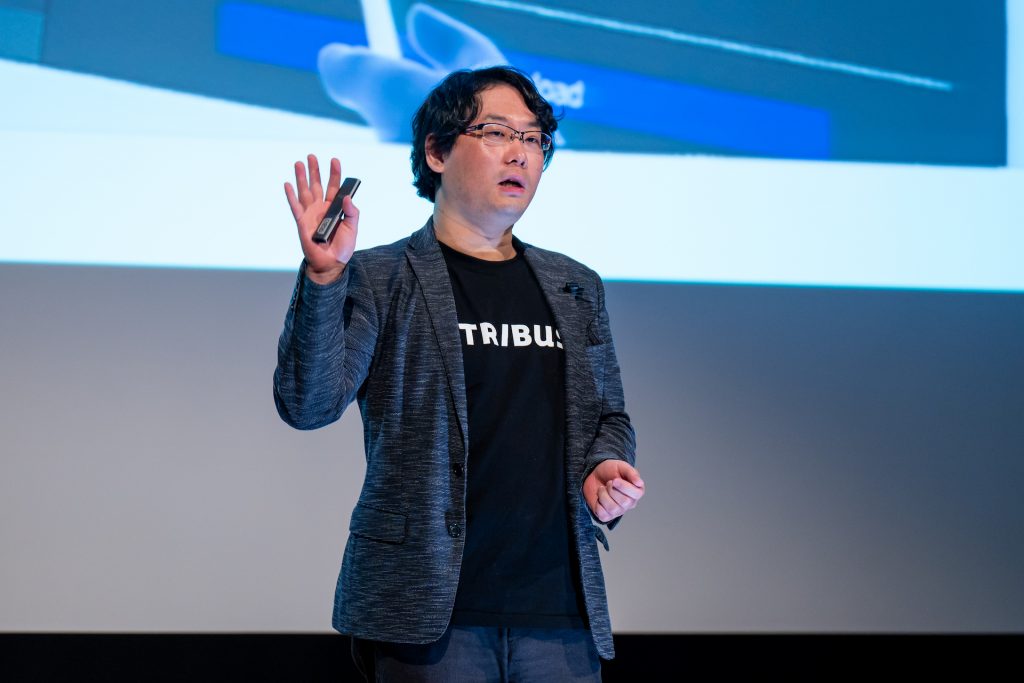
「VRでリアルよりも便利に働ける世界を作る」をビジョンに掲げ、「リコーバーチャルワークプレイス」を提供してきました。お客様の任意の空間をVR上で再現し、各自がVRヘッドセットを使ってその空間に一堂に会することが可能なソリューションです。これまで様々な建築現場で活用されてきました。卒業式では引き続き事業化を目指すという前向きな締めくくりとなりました。
冒頭、前鼻毅氏は自身のチームについて、「全員リコーITソリューションズの出身で、ほとんどがエンジニアのメンバー構成になっており、戦略や販売が弱いチームでした。しかし、この活動を通して戦略や販売などを学び、協力を得ながらやってきました。」と、社内のリソースを活用する社内起業ならではの背景を語りました。
図面や画像、動画など、様々なメディアのデータをデジタル空間に再現し、組み合わせて見ることができるのがバーチャルワークプレイスです。
実際に多く使用されたのは建築現場とのこと。渋谷の駅前をスキャンしデータを再現、その中に入り込みコミュニケーションすることができた事例を実際の映像と共に紹介しました。
活動は2020年の東京建設株式会社とのニュースリリースをきっかけに一気に飛躍しました。2021年には鹿島建設株式会社との取り組みで大きな成果を出すことができ、業績を拡大していきました。
当時の様子を前鼻氏は「現場の張り付き等も行っていまして、主に2週間くらい、毎朝8時から作業者の人と一緒にラジオ体操をやっていました」と語りました。
卒業式後、引き続き事業化を目指すRxRチームは「成功が最大の恩返しと思っておりますので、引き続き頑張ってまいります。」と締めくくりました。
一期生の審査をしていただいた方々に祝辞を頂きました

株式会社Spiral Innovation Partners ジェネラルパートナー 岡洋氏
皆さんの頑張りが伝わってきて感極まるものがありました。一歩目にチャレンジをして、5年間挑戦された皆様の頑張りに改めて拍手を送りたいと思います。皆さんのチャレンジが次につながっているということを忘れないでいただきたいということと、誇りに思っていただきたいです。事業をやっていく上での感動を忘れずに、それからチャレンジし続けたことを考え、行動し、歩みを止めず、これからの挑戦に生かしていただけたらと思います。

リコーデジタルサービスビジネスユニット プレジデント 入佐孝宏氏
皆さんのプレゼンテーションをお聞きして、大変心に刺さりました。おそらくこの日本という国がもっともっとイノベーションを起こせる、その装置を我々はリコーの中に持っていて、それが他社にとっても役に立つ、そういう6年目に向かっているのだと思います。TRIBUSは続いていきますので、これを牽引する皆さん、サポーターの皆さん、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

リコー 顧問 赤羽昇氏
本当にチームの皆さんおめでとうございます。私は5年前より以前から、プログラムで採択されたチームに、事業化に向けてどのような行動をするかというところから入っています。事業として成功したかどうかはまだわかりません。どのチームにしても難しいところもあるでしょうしさらに良くなるチームもあると思います。しかし、キャッシュを大事にする、自分の裁量で決める、人件費すら無限ではない、時間も無限ではないという感覚が身についたということにびっくりしました。

リコー 未来デザインセンター 所長 駒場瑞穂氏
それぞれの方の専門分野を超えて、また中にはリコー初や、日本初など、もしかしたら世界初のチャレンジをしてきたチームもあるかと思います。まずそのことに敬意を表します。今後も、さすがTRIBUSの卒業生だと言われるような活躍を期待しています。

リコー 先端技術研究所 所長 山田泰史氏
卒業生の皆さん、本日はおめでとうございます。先端技術研究所は長いこと、新規事業を20年、研究所は30年以上やっていますが、本日はやはり皆さんを見ていて初心に戻らなければならない、そして暗い顔をしていると新規事業は成長しない、新しいことは楽しみを持ってやらなければならないと言うことを、改めて皆さんの発表を拝見して思いました。

リコー 代表取締役会長 山下良則氏
2019年の最初のピッチはホールに400人ぐらい集まりました。社外の方にも来ていただいて、社外の審査員の方々にピッチを褒めていただいたこと、夢も語ってもらったことを今でもすごく思い出します。当時、私自身もピッチを聞くのが初めてでしたので、何をどう質問したらいいのか分かりませんでした。私自身も勉強しながら、当時恐る恐る質問を行いまして、時間制限が厳しく、まるで試験されているような会だと思っておりました。皆さんも当時は練習した言葉で話していましたが、本日は本当に自信に満ちていて、成功や失敗などとは違うところで成長を感じました。
皆さんのおかげでやっとこの取り組みを行ってもいいと、幹部も含め、カルチャーが根付いてきたと思います。
TRIBUSだけでこの会社が変わっていくとは思っていませんが、皆さんの声で運用を変えていく制度にしていかなければいけない、様々なことで声を出す会社に成長していければと、考えております。新しい事業に転換が進んでいくという確信を本日感じました。取り組みに参加をしていただくということが、すごく大事な経験であり、会社への貢献であり、その先の社会貢献であるという風に思っていただきたいです。
最後に、挑戦者の方を見て思いました。昔から好きな言葉で、1902年に豊田 佐吉、いわゆる豊田自動織機の創業者がその当時話していた、「その障子を開けてみよ、外は広いぞ」この言葉で私はずっと生きてきました。誰しもが持っている恥ずかしいという心の中の障子を、どのぐらい勇気を持って開けられるかは、個人の問題ではなく、組織の雰囲気や仲間などが、後押しをしてくれるのだというのを最近感じています。
ぜひTRIBUSにチャレンジしたいと思っているリコーグループ社員の方も、全く興味のない方も含め、皆さん仲間ですので、この会社を変えていければと思います。今日はどうもありがとうございました。
TRIBUS1期生の皆さんは、TRIBUSで得たかけがえのない経験・知見を活かしそれぞれのネクストステージに進みます。TRIBUSは引き続き「事業」「人」「挑戦する文化」を育んでいき、共創イノベーションの環をさらに拡大してまいります。これからもTRIBUS、そして新しい価値創造に挑戦するチャレンジャーの皆さんへの応援をよろしくお願いいたします。
