【Challenger’s Interview】モットーは「建設業界の常識を、ひっくり返す」。圧倒的な現場目線で建設業のDXを加速させるCONOC
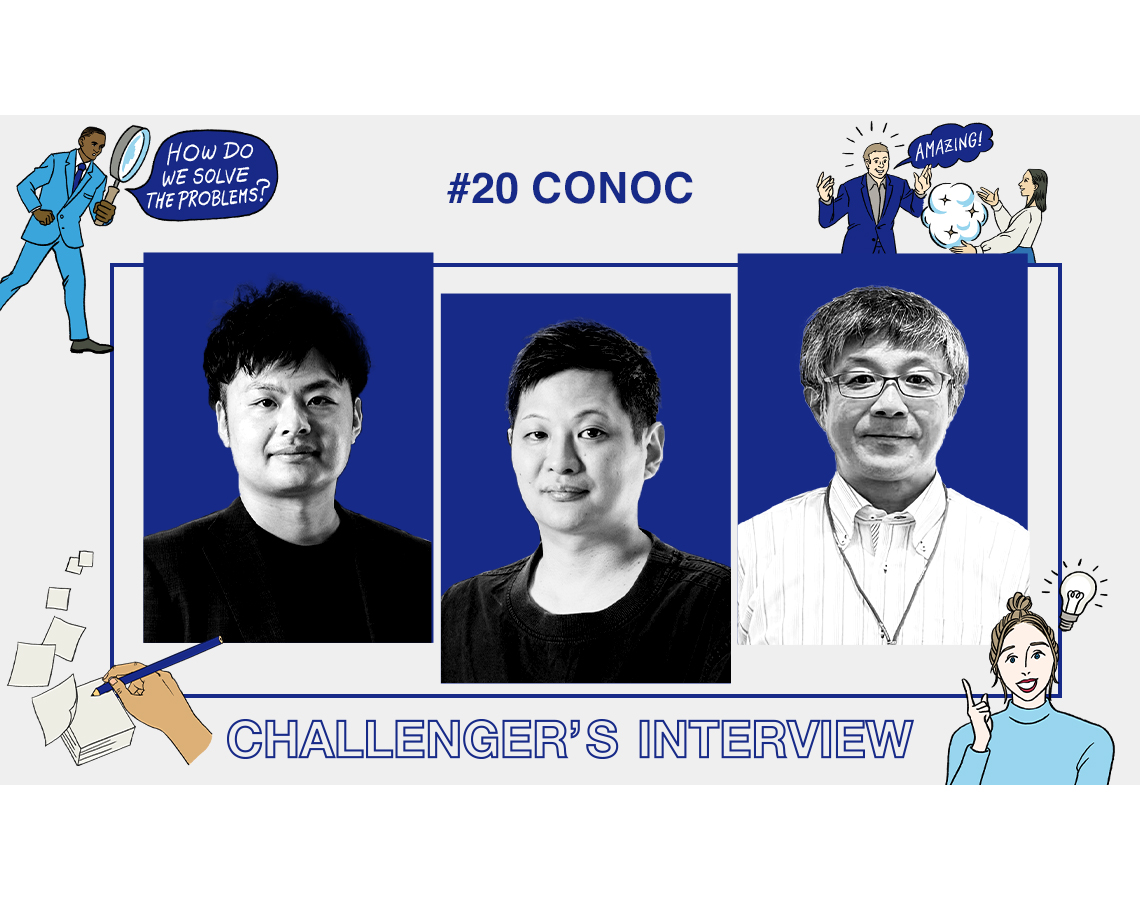
「TRIBUS2023」の成果発表会「TRIBUS Investors Day」で脚光を浴びたCONOC(コノック)。「建設業界の常識を、ひっくり返す」をコーポレートステートメントに掲げ、建設業界の中小工務店向けにDXソリューションを提供するスタートアップは、圧倒的な現場目線で建設業のDXを加速させるべく、業界初のAI機能を搭載した多彩なサービスを展開している。株式会社CONOCの佐戸充氏と千賀弘瑛氏に、TRIBUSに応募したきっかけやアクセラ期間中の取り組み、期間終了後の新たな展開に至るまで、カタリストを務めた津田氏を交えて話を伺った。
佐戸充氏
株式会社CONOC 取締役
千賀弘瑛氏
株式会社CONOC セールス
津田道彦
TRIBUS2023カタリスト リコーデジタルサービスBU デジタルサービス開発本部 日本極第二開発センター 第一業種DX室 SDC福岡グループ
建設業の業務効率化&生産性向上を実現するコンテック事業
――最初に、CONOCの事業について教えてください。
千賀 私たちは、建設業における業務効率化や生産性向上を実現するとともに、新たな価値を創出するサービス開発に取り組んでいます。建設業のアナログな業務管理・書類管理・施工管理のDX化を図り、属人的な業務をなくし、シームレスな業務連携を実現するために、「Con-tech(コンテック)事業」を展開しています。
コンテック事業の柱の一つは、建設業の見えにくい要素を可視化し、業務改善・収益増加を実現するためのクラウド型の業務管理ツール「CONOC業務管理クラウド」です。もう一つは、現場管理を可視化し、業務の適正化と業務連携強化を目指すクラウド型の現場管理ツール「CONOC現場管理クラウド」。そして、3つ目は、電子帳簿保存法に対応した工事ごとに、書類・写真を管理・共有できる建設業特化型のクラウドストレージ「CONOCクラウドストレージ」です。これら3つのクラウドサービスを連携させることで、建設業に関わるすべての業務を包括的に一元管理できる仕組みとなっています。
※Con-Tech は、Construction(建設)×Technologyの略。
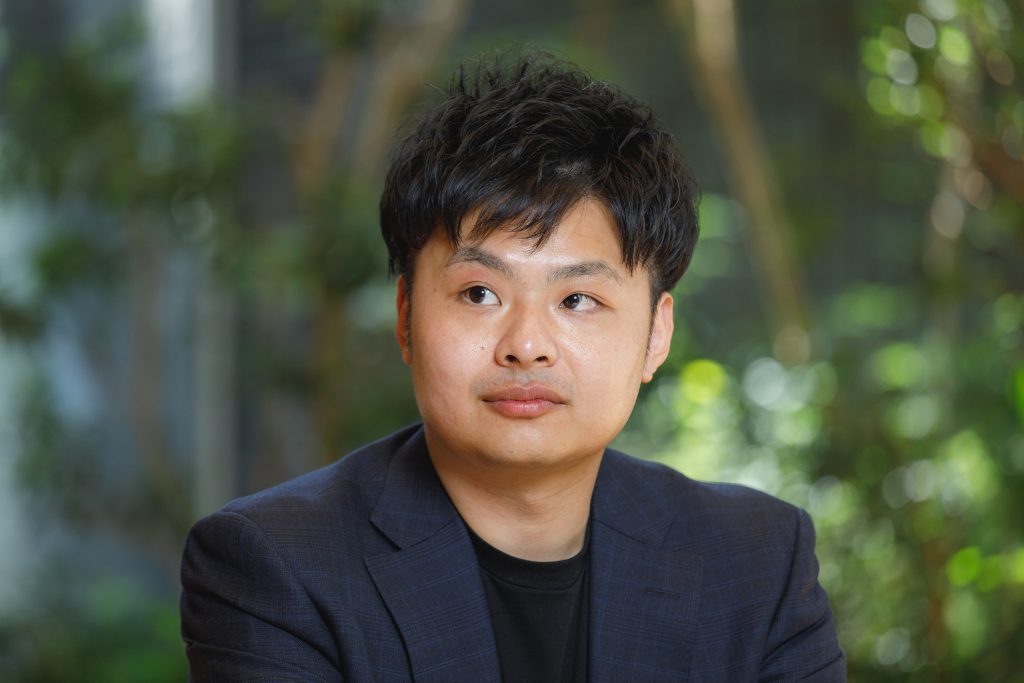 株式会社CONOC セールス 千賀弘瑛氏
株式会社CONOC セールス 千賀弘瑛氏
――TRIBUS2023に応募したきっかけを教えてください。
佐戸 TRIBUSに応募させていただく以前から、リコーさんが開発・提供する360度カメラ「THETA」に、大きな魅力を感じていました。リコーさんの社内の方に伝手があったので、当社が展開するクラウドサービスとのAPI技術連携で共創できないかと思い尋ねてみました。その当時は、他社とのプロジェクトが進んでいたとのことで実現には至らなかったのですが、THETAと連携できたら理想的だなとずっと思っていました。そんな折、TRIBUSの存在を知りました。採択されれば、新たな切り口からTHETAとのAPI技術連携にアプローチできる可能性があるかもしれないと思い、応募させていただくに至りました。
 株式会社CONOC 取締役 佐戸充氏
株式会社CONOC 取締役 佐戸充氏
――アクセラ期間中は、どんな取り組みを行いましたか?
千賀 TRIBUSに参加させていただくにあたって、THETAと当社のプロダクトのAPI技術連携を図ることにより、建設業界の中小工務店の業務効率化や生産性向上を加速させることを目標としていました。その意向を汲み取ってくださったカタリストの津田さんのご尽力により、担当部署の方とおつなぎいただき、API技術連携の話をスムーズに進めることができました。
アクセラ期間中は、API技術連携の確認をはじめ、サービスの概要設計、リコーさんの関係部署とのリレーション構築、市場のニーズを確認するためにクライアントへのヒアリングを実施しました。ヒアリングは、リコーさんと当社のお客様の双方に行ったのですが、貴重な意見を多くいただきました。THETAのことを知っている方からは、「THETAを建設業の業務課題を解決するために活用するのは、すごくいいアイデアだと思う」「建設業界の未来がイメージできる」といった好意的な声があがりました。その一方、THETAを初めて知ったという方からは、「便利になるのか、あまりイメージが湧かない」という意見も、正直ありました。
18歳より現場の職人としてキャリアをスタートした弊社代表の山口一と同様、私自身も前職ではオフィスや公共空間の内装工事の現場で従事していました。その経験から誤解を恐れずに言うと、建設業の現場を担う多くの方は、まだまだデジタル技術に疎い傾向にあります。その意味でも、これまで市場になかったものをいきなり理解するのは難しいところもあるのではないかと思いました。それと同時に、訴求の仕方に趣向を凝らせば、プロダクトのメリットをイメージすることができ、ひいては、世の中に普及させていくことができるのではないかとも思いました。ヒアリングを通じて、今後に活かせる多くのことを学ばせていただきました。

長期的視点での共創、社内起業家の情熱から得た学び
――カタリストの津田さんは、CONOCのどこに魅力を感じたのですか?
津田 CONOCさんが、20年以上の工務店経験を元に、コンテック事業を展開しているスタートアップだと知り、そのユニークさに惹かれました。建設業のお客様にヒアリングを行った経験や、THETAの画像に関わる業務での経験を活かして、伴走させていただきたいと思い、手を挙げさせていただきました。
 リコーデジタルサービスBU デジタルサービス開発本部 日本極第二開発センター 第一業種DX室 SDC福岡グループ 津田道彦
リコーデジタルサービスBU デジタルサービス開発本部 日本極第二開発センター 第一業種DX室 SDC福岡グループ 津田道彦
――カタリストとして伴走する中で得られた気づきや工夫したことがあれば教えてください。
津田 先ほど千賀さんがおっしゃった通り、CONOCさんが目指されていたのは、THETAとのAPI技術連携を図ることで、建設業における業務効率化や生産性向上に資するクラウドサービスを展開することです。その実現のために必要な社内のリソースとうまくつなげられるよう、力を注ぎました。現在、私は開発の部署で従事していますが、営業職の経験や販売現場との接点もあるので、持ち得る知見を活かしてフォローさせていただきました。
基本的に、CONOCさんの拠点は東京、自身は福岡ですので、当初はうまくやりとりできるのかと少し不安でした。そんな中、福岡を拠点にされているCONOCさんのCTOの方と、偶然、別件でお会いする機会がありました。その場で、TRIBUSの件についてもお話しさせていただけたこともあって、地の不利を感じることなく、うまく伴走することができたと思っています。
――――佐戸さん、千賀さんは、どんな気づきがありましたか?
佐戸 当初、約3ヶ月の検証期間中にすべてをやり切らなくてはならないのかなと思い、内心、焦る気持ちもありました。しかし、「TRIBUSが終わったら、それで終わり」ではなく、長期的視点での共創を考えてくださっていることを身を持って実感できて、大きな安心感を得られました。現在に至って、手厚くフォローしてくださっていることがありがたいです。

千賀 社内起業家の方たちのイノベーションにかける情熱に、大変刺激を受けました。アイデアの素晴らしさにも感動しましたが、日本を代表する大手企業のリコーさんの社内から、革新的なビジネスの種が生まれていることに触れ、「私たちも負けてられないぞ!」とモチベーションが高まりましたし、大きな学びになりましたね。リコーさんという会社そのものに革新的なマインドがあるからこそ、TRIBUSが生まれたのかなとも思いました。
さらなる共創。その先に描くCONOCの未来
――TRIBUS終えてからの共創活動について教えてください。
千賀 現在は、アクセラ期間中に検証した内容をもとに、リコーさんの担当部署の方々と手を携えながら、サービスの開発を進めているところです。THETAが素晴らしいのは、360度で撮影することによって、1枚の写真では得られない圧倒的な情報量を得られることだと思います。例えば、床だけでなく、壁や天井も見られるとなると、写真そのものの価値が大きく変わります。「この現場はここに注意した方がいいですね」という風に、事前に現場を確認することもできますし、さまざまな面で施工に役立てることが可能になります。
CONOCが展開しているサービスの一つ「CONOCクラウドストレージ」には、現場の方にとっての見やすさを配慮した上で設計した写真共有の機能があります。これをTHETAと連携させることによって、現場に関わるさまざまな人たちが同じ現場のデータを見られるようにすることを目指して、今後も力を注いでいきたいと思います。
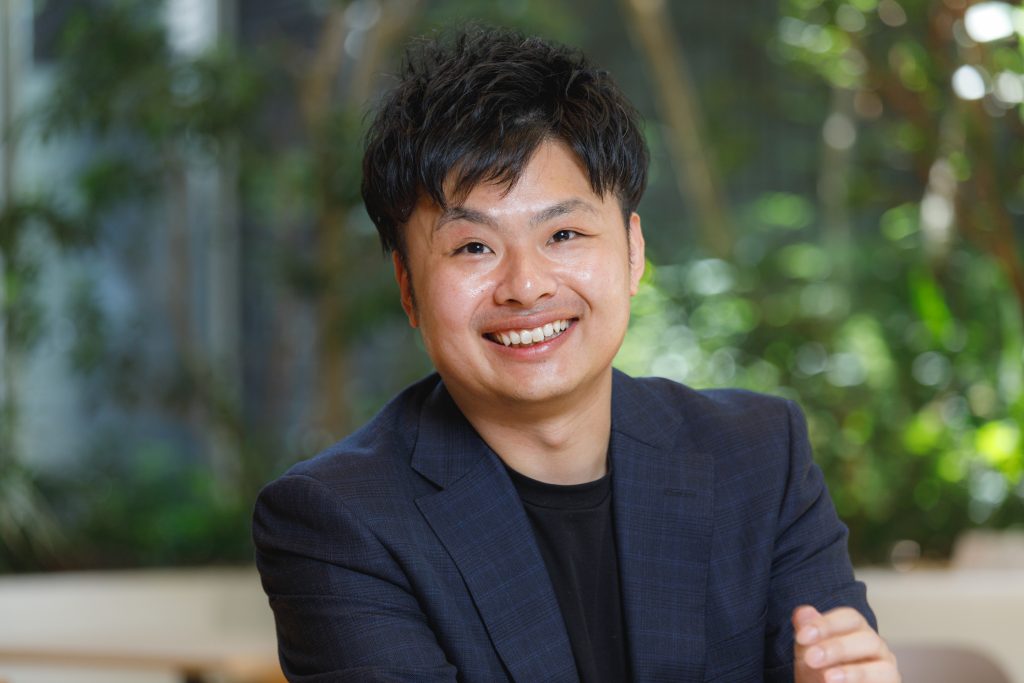
――「TRIBUS Investors Day」で、「THETAדx”でTHETAの付加価値を向上させていきたい」とおっしゃっていたことが印象的です。その“x”の一例を挙げるとしたら何になりますか?
千賀 今後、AIはやはり必要になってくると思っています。現場の親方たちがすごいのは、長年の勘と経験をもって、「これは多分こんな問題が起きるぞ」と気づいて、その前に打つべき手を考え、実行に移せることです。しかし、そのノウハウは親方たちの中にあるものなので、私の知るかぎり、明文化されてはいません。AIは、そうした情報を学習するのが上手なので、活用することができますし、活用するべきだとも思います。人間の良さは、それらの情報を超えて「気づく」ことだと思うので、ある程度のところまでAIに頑張ってもらい、最終的には人の勘と経験でしっかり現場を収めていくというような未来を描いています。
施工の工程表やプロジェクト管理においても、AIは活用できると思います。「こんな工程を組んでおくと、問題なく当初の予定通りに進行できるだろう」といったことも、AIなら導いてくれる未来が見えています。こうしたことを実現できれば、さらなる業務効率化や生産性向上を実現することにもつながってくると思っています。
――最後に、今後のCONOCの展望について教えてください。
佐戸 これまでお話ししてきたように、現在は、建設業の現場にいる方たちやバックオフィスを担う方たちに向けたサービスを事業の主軸としています。今後は、弊社代表の山口一が一つの目標としている建設業界のネットワークの構築にも力を入れていく考えです。中小工務店が抱える現場の労働力不足を解決するために、人材の共有の必要性なども出てくると思います。そうした課題に応えられるよう、CONOCスタッフ一丸となって邁進してまいります。「建設業界の課題なら、CONOCで解決」が広く浸透することを目指して、これからもより一層の力を注いでいきたいと思います。

PHOTOGRAPHS BY UKYO KOREEDA TEXT BY Yuriko Kishi
