「TRIBUS 2023」の成果発表会「TRIBUS Investors Day」開催レポート<Part1>

2月8日(木)、事業共創を目指す社内外統合型のアクセラレータープログラム「TRIBUS 2023」の成果発表会「TRIBUS Investors Day」が、株式会社ユーザベース本社 丸の内オフィスで開催されました。昨年10月の統合ピッチで採択された社内起業家9チームと、リコー各事業部との連携・実証実験を進めてきたスタートアップ企業9社が登壇し、その後の成果を発表しました。レポート<Part1>では、社内起業家9チームによるピッチの内容をご紹介します。

冒頭、株式会社リコー代表取締役会長の山下良則は、次のように開会の挨拶を行いました。
「実は一昨日、2月6日はリコーの88年目の創立記念日でした。リコーは長い歴史を持つ会社ですが、リコー三愛グループの創始者・市村清が、ベンチャーマインドを大切にした起業家であったように、世の中がこれだけ大きく変わる中、私自身も常にベンチャーマインドを持っていたいという想いで、2019年にTRIBUSをスタートしました。この3月には、社内起業家1期生がTRIBUSを卒業し、それぞれのネクスト・ステージに進むことになりました。事業を軌道に乗せたチームもあれば、撤退するチームもありますが、それはそれで社員はすごく成長しましたし、これからの活躍に期待しています。5期目を迎えた今、このプログラム自身が成長していることを実感しています。本日、ライブ配信を試聴してくれているリコーグループの社員には、社内起業家とスタートアップの方々が交流し刺激し合えるこの場所をどんどん活用して欲しいです。そして、これから登壇する皆さんには精一杯、力を発揮していただきたいと思います。我々も、精一杯審査をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします」
社内新規事業チームのプレゼンテーション
Investors Dayの前半は、社内起業家9チームのプレゼンテーションが行われました。ここで最終審査を通過し、TRIBUS推進室に採択された3チームは、新規事業の立ち上げ・事業化に本格的に取り組んでいくことになります。 ※以下、事業概要/所属/代表者名の順
1. 工場の人手不足対策事業
リコーエレメックス株式会社 酒井隆敏
リコーエレメックスの酒井氏が率いるチームが考案したのは、少量多品種を製造する中小メーカーの人手不足を解消するためのものづくり効率化アプリです。アクセラ期間中は、スケジュールを自動化するだけでなく、サイクルタイムの自動測定を可能にしたアプリの開発に力を注いできました。
従来のバーコードから重量計に切り替えてサイクルタイムを自動測定することで、「測定にかかる時間を大幅に削減するだけでなく、いつ、どの工程が完了したかを自動で共有できるようになった」と言います。今後は更なる生産性向上を図るために、サイクルタイムの自動化の改善に注力しながら、事業化に向けて販売体制を整えていきたいと述べました。
質疑応答では、サイクルタイムに着目した検証活動を評価する声や課題設定に関する質問が寄せられました。
2.知的障がい児を笑顔にするモノ・コト創出事業
リコーエレメックス株式会社 杉山忠司
杉山氏のチームが、「働けない人にも喜びを」与えるための最初の商品として考案したのは、外食できない知的障がい児を外食できるようにする外食用充電式ミルサーと、ミルサーを使用可能な飲食店の検索サイトをセットで提案するビジネスプランです。
Investors Dayまでの約3ヶ月間は、ミルサーを供給するOEMメーカーの探索やプロトタイピングによる実証実験と併せて、ミルサーを設置可能な店舗があるかどうかを検証しました。
「ミルサーを持ち込み可能としている飲食店は多く、承諾をいただいた店舗はウェブサイトで紹介しています。一方、ミルサーの設置については、厚生労働省のHACCP(ハサップ)に沿った食品衛生管理の制度化に伴い、難易度が高いことが分かりました」。打開策として嚥下食提供店にアプローチしたところ、店頭に設置することで「嚥下食を追加工したい」という顧客要望に応えられることが新たに分かったそうです。
質疑応答で、杉山氏は知的障がいのある自身の息子さんとの経験を熱く語りました。「検証期間中、ミルサーを持ち込める5店の飲食店へ行き、実際にミルサーを使ってみました。ラーメンからフランス料理まで、息子は初めて口にする料理をとても美味しいと感じていたようです。同じ課題を抱える親御さんとそのお子さんにも同じ感動を味わっていただきたい。これからもその一心で、事業化に向けた活動を続けていきたいと思います」。
3.エチオピア地方都市向け買物支援サービス
株式会社リコー 塚原みな
青年海外協力隊として、エチオピアの地方都市ジンマに2年間滞在した経験を持つ塚原氏。品質の良い日用品を手に入れるためには、片道8時間かけて首都まで行かなくてはならないことに問題意識を感じていたと話します。
そんな氏の原体験から生まれたのが、「エチオピア地方都市向け買い物代行サービス」です。利用者が人に頼む手間や心理的な負担をなくす、商品ラインナップを充実させる、破損、紛失、欠陥商品、詐欺などのリスクを回避する。これら3つの課題を同時に解決する手段として買い物代行サービスとショッピングアプリを考案し、現地で検証を実施しました。その結果、顧客48名に声かけし新規流入を含め計9名が受注決済まで完了し、50店舗中47店舗がアプリへの商品掲載を承諾するなど、ビジネスのモデルの妥当性を確認できたと言います。
「買い物の課題は、アフリカ各国が抱える課題です。私たちは、このサービスを通じた認知獲得と取得したマーケティングデータを基にしたAI開発などデジタルサービスでアフリカ進出への足がかりにしたいと考えています。来年度は、更なる商品ラインアップ拡充のための店舗への営業活動、オペレーション方法の確立などの準備を進め、地方都市でのサービス開始をめざしています」と述べピッチを締めくくりました。
4. ドローンの国家資格取得に向けた練習支援サービス
株式会社リコー 亀井謙二
亀井氏のチームが考案したのは、ドローンの国家資格取得に向けた練習場所の提供サービスです。今回の検証期間では、フットサルコートだけでなく、屋内テニス場などの協力を得て、ドローンの練習場所を計7ヶ所に拡大し、空き状況の確認や注意事項への同意、練習場所の予約を行えるホームページを開設し、検証を行いました。
その結果、練習場所までのコストを2分の1に削減することに成功。割り勘制度を導入し、利用者の費用負担を軽減する付加価値も生み出しました。利用者からは好反響を得ましたが、利益率が4.5%と少ないため、亀井氏はドローンを扱う大企業向けに、月額制で利用チケットを付与するビジネスモデルを新たに考案しました。提供価値を検証するために練習会を開催したところ、5社が参加し、その8割が「またサービスを利用したい」と回答したそうです。
「練習場所の提供により収益性を確保していくと共に、今後は、点検業界における人材不足の課題解決にも取り組んでいきたいと思っています」と意気込みを語りました。
質疑応答では、リコーのドローン活用支援サービスとの連携、点検業界に着目した理由、場所を貸してくれる側へのメリットなど、細かな点で質問が相次ぎました。
5.フレイル期の高齢者に「できる」を提供する事業
リコージャパン株式会社 三谷悠貴
祖母が免許の返納をきっかけにして家に引きこもり、急速に衰えて行ってしまった体験から「高齢者が明日できることがあってやりたいことがある社会を作る」というミッションを掲げる三谷氏が開発したのは、屋内にいながら自分の足で進むことができる散歩を体験できるソリューションです。自分の意志で好きな景色を見ることができる見回し機能や、遠隔で知人と会話できる機能も備わっています。
Investors Dayまでの検証期間にテスト販売を実施。高齢者のコミュニティや個人など、4件の契約が発生し、継続利用に至りました。利用者からは、「けがをして外出頻度が減っていた妻と一緒に出かけられる」「コミュニティのみんなで、海外旅行にも行ける」といった声が寄せられました。介護施設からも利用意志を確認できたそうです。
「今後は高齢者の自宅や施設、コミュニティにエッジデバイスを導入し、みんなで出かけられる体験を提供していく予定です」と三谷氏。高齢者が長期的に利用し続けたいと思うような仕掛けづくりや、このシステムを通じたコミュニティやイベントが成立するかを検証したいと話しました。
質疑応答では、「前回から検証活動がすごく進んでいて、熱意が伝わってきた」という意見が複数上がった一方、「外出できなくなった方が家庭に備えるものとなると、エントリーのハードルが高いので、エンターテインメントとして導入できる工夫があるといいのでは?」といった助言もありました。
6.可食性コーティングによる食品ロス削減
株式会社リコー 植平将嵩
バイオ素材と印刷技術を通じて食品ロスの削減をめざす植平氏のチームは、その解決策として、「鮮度維持コーティング」と「食品のデジタル管理」を提案しています。
今回の検証期間では、鮮度維持コーティングを施したバナナを用いて国内でテスト販売を実施し、市場の受容性を確認した上でグローバル事例を分析しました。「私たちが開発する鮮度維持コーティングの強みは、一般に食用とされる素材を原料に使っていることです。これは他社にはない重要な差別化要素であると考えています」と植平氏。
独自に開発したコーティングのレシピと塗布工程を流通会社にライセンスし、流通会社は、コーティングを青果物に塗布して小売店に販売するというビジネスモデルです。大学との共同研究により技術開発を進めながら、リコーのインクジェットの開発基盤を活用することで開発効率を活性化させ、世界最速のQR印刷システムを用いてトレーサビリティを確保することなども視野に入れていると話しました。
「食品ごとの最適なコーティング厚の設計など、技術課題はさまざまにありますが、国内で最も実績のある研究者や青果物の流通会社、素材メーカーといった心強い協力者に恵まれています。オープンイノベーションの精神で果敢に取り組んでいきたいです」と氏は胸を張りました。
質疑応答では、「技術課題は多いかもしれないが、廃棄されている食品はバナナだけでなく、大きな可能性を秘めた事業だと思う」と山下会長がエールを送りました。
7.忘れ物防止や持ち物管理の支援事業
リコーITソリューションズ株式会社 木田夕菜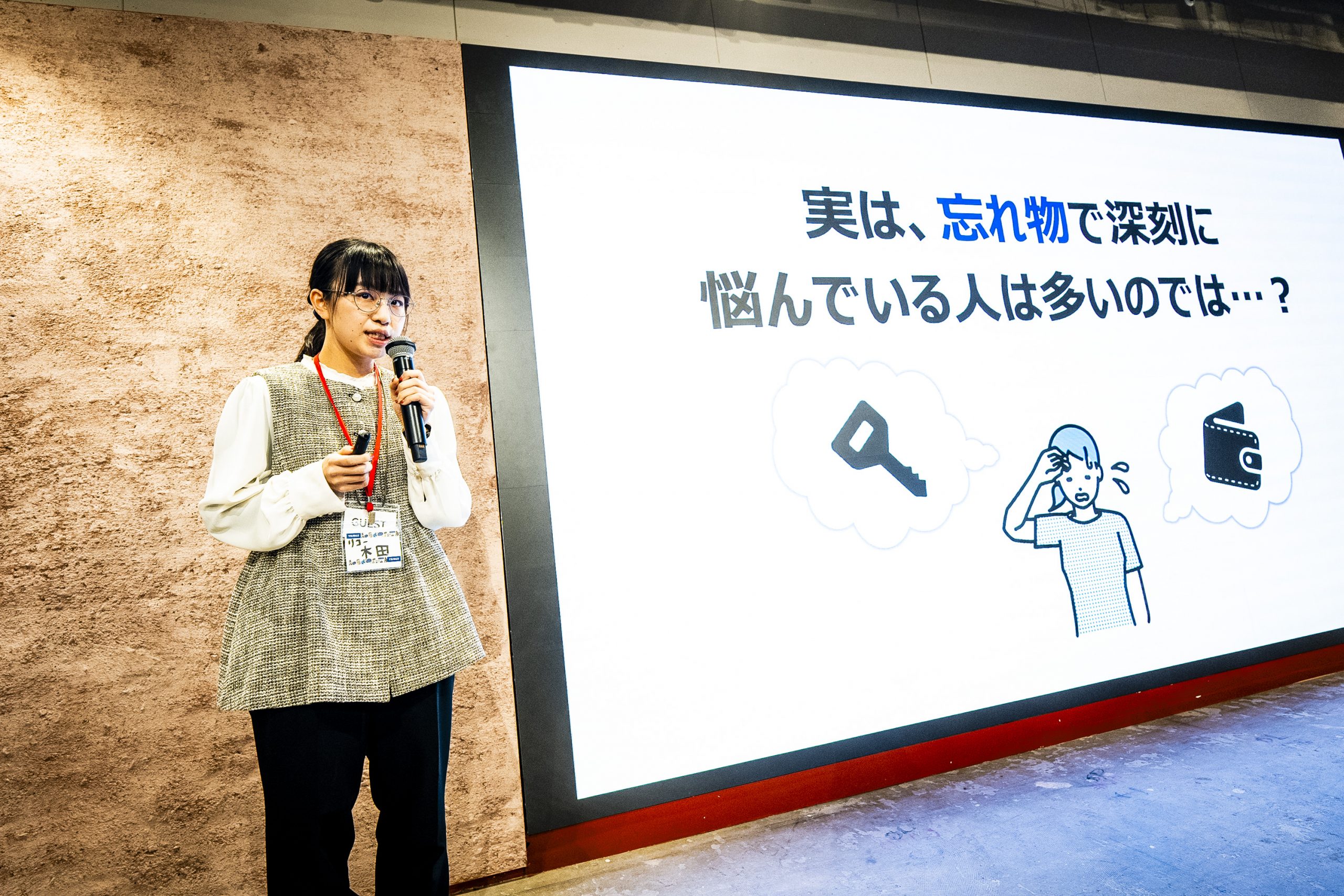
木田氏のチームが考案したのは、忘れ物や持ち物の準備に困っている人を支援するソリューションです。アクセラ期間中は、予定の発生から持ち物の入れ忘れの確認までをワンストップでサポートするプロトタイプの検証を行いました。
ADHDやASDの傾向のあるユーザー13名に使ってもらったところ、「忘れ物が減らせた」「自己肯定感につながる心理面にポジティブな変化を感じた」など、好意的な評価が得られました。一方、「ソリューションの価値を実感したが、月額6000円の利用料は高い」と回答した人が多かったため、月額1980円に再設定し、操作性の改善も含めて検証に臨んでいくとのことです。
「顧客ターゲットになり得る人は、少なくとも100万人います。忘れ物に困っている当事者の方々が成功体験を積み重ねることで、ウェルビーイングと自信につながる社会を実現していきます」と木田氏は締めくくりました。
質疑応答では、「ターゲットとする顧客の外出傾向について教えて欲しい」「月額1980円でも少し高いと感じる人がいると思うが、それでも利用したいと思ってもらえるような工夫を議論している?」など、ユーザーに関する質問が多く上がりました。
8.シニア人材に特化した就職支援事業
株式会社PFU 四禮光正
統合ピッチ以降、四禮氏が率いるチームは、顧客企業と課題の絞り込みと提供価値に重点を置き、検証活動を進めてきました。フィールド調査を行った結果、社員数が400~700人規模の企業では、社内システム人材が深刻に不足していること、DXプロセスの中でも運用フェーズにおける人材が不足していることが分かりました。
「400~700人規模で、製造業、建設業を営む企業に対し、リコーグループ内のDXやシステム領域に携わるシニア人材の方々をマッチングしたいと考えました。そこで、社内のシニア人材14名をリストアップし、シニア人材マッチングサイトを制作し、想定顧客に対して利用価値とニーズがあるかどうかを検証しました。長年ビジネスに携わる中で培ってきたスキルと知見をあわせ持つリコー社員の方なら、ぜひご紹介願いたいといった声を多くいただきました。このスキームによって、人材不足やDX推進に悩む企業の課題を解決すると共に、シニア人材の皆さんには、セカンドキャリアを実現することで、はたらく歓びを叶えていただけると思っています」
質疑応答では、企業へのヒアリングを行った中で見えてきた新たな需要やシニア人材の勤務形態などに質問が集まりました。
9.宇宙映像事業
リコーテクノロジーズ株式会社 武田謙郎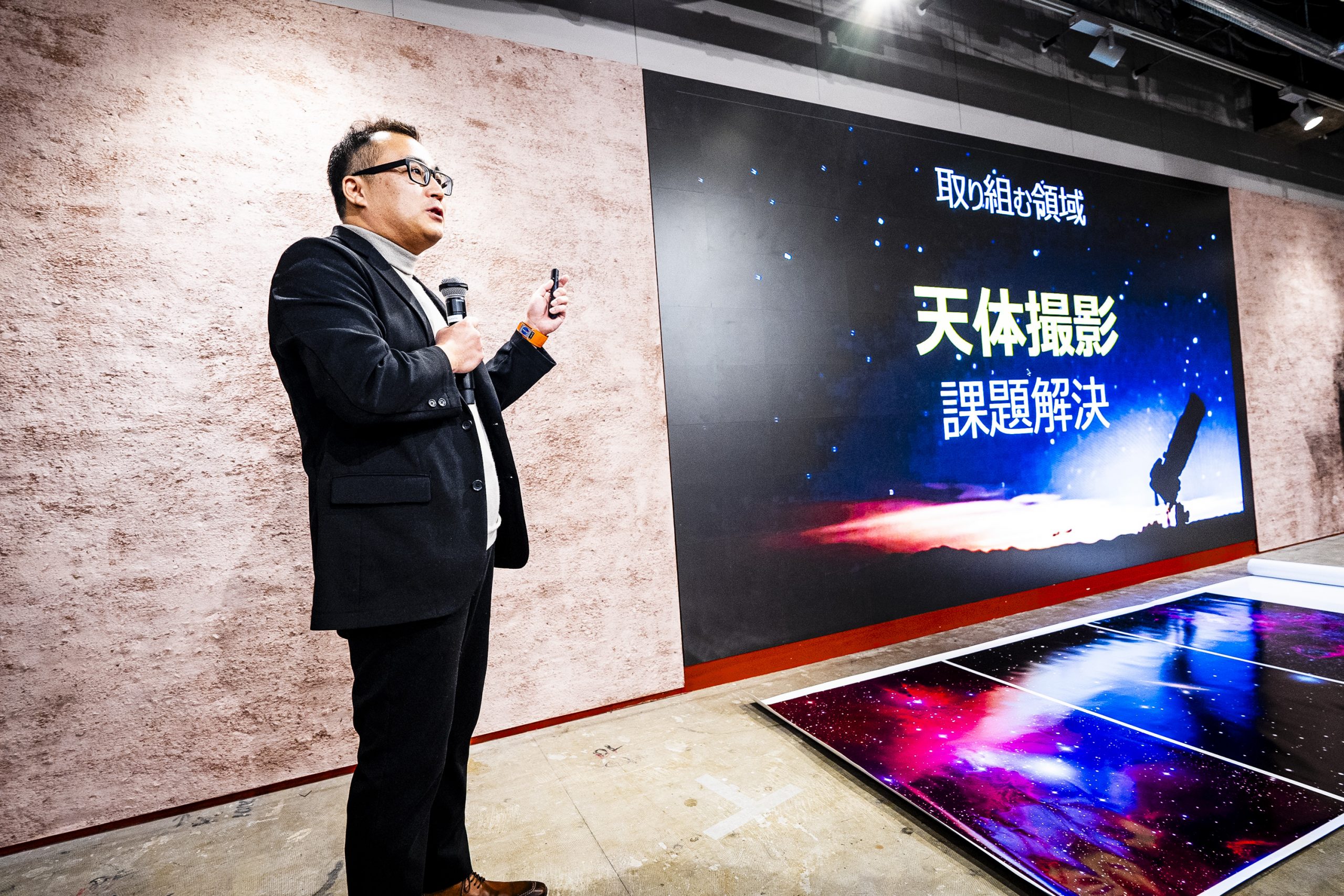
武田氏が率いるチームは、「海外リモート望遠鏡サービスを国内の個人天文家に使ってもらう実証実験を実施し、リピートの要望も多く得られた」と統合ピッチで報告しました。今回の検証では、天体撮影のレジェンド3名にもサービスを使ってもらい好評を得るとともに、レジェンドの協力のもと、天文専門誌に3号連続で撮影した天体映像作品が掲載するに至り、同誌編集長からも熱いエールが送られたのだそうです。
Investors Day通過以降は、本格的なサービスの提供準備に取り掛かる予定で、すでにポータルサイトの開発検討やプロモーションの検討に着手していると言います。
「第2弾に向けた仮説検証として、引き続き、様々な方へのインタビューを継続しており、病院に入院している子どもたちへのインタビューも進めているところです。私たちは、このサービスを社会的に意義のある事業に育て、新しい宇宙の楽しみ方を提供できると確信しています」
質疑応答では、社外審査員の土井雄介氏が「1年前に壁打ちした時と比較して、武田さんやチームの皆さんが、リモート望遠鏡の検証にここまで素直に向き合えることに感動しました。まさに、人が覚醒する瞬間を見させてもらったと感じています」とコメントしました。そのほか、海外での事業展開の可能性や保守コストなどの細かい点について質問が寄せられました。
TEXT BY Yuriko Kishi
