「TRIBUS 2022」の成果発表会「TRIBUS Investors Day」開催レポート

先に報じられたように、事業共創を目指す社内外統合型のアクセラレータープログラム「TRIBUS(トライバス) 2022」の成果発表会「TRIBUS Investors Day」が7月20日に開催され、社内起業家3チームが「TRIBUS社内起業賞」に選ばれました。また、2月の統合ピッチ以降、リコー各事業部と連携・実証実験を進めていたスタートアップ企業5社のうち4社が、その後の成果を発表しました。ここでは改めてイベントの模様をお伝えします。

Investors Dayの前半は、社内起業家チームのプレゼンテーションです。開会にあたり会長の山下良則は、今年がTRIBUSにとって節目のひとつとなりそうだと話し、「さらなる成長を」と期待を語っています。
「今日の最終選考を通れば、社内起業家チームの皆さんは、TRIBUS推進室に異動や兼務となり、2~3年かけて専従で事業化に取り組んでいただくことになります。そして、第1回TRIBUSの受賞チームが、いよいよ卒業の時期に来ているのが今年。それぞれが違う形、ステージで活躍するか、撤退するかを判断することになる大事な時期です。これはまた、TRIBUSという取り組み自体が成長できるかどうかの指標にもなると思います」
外部のスタートアップ企業に対しては、リコーのような大きな企業にとって、今後ますます必須の存在になってくるだろうと述べました。
「リコーもなんだかんだ言って大企業と呼ばれる企業のひとつで、大企業としての強みもあれば弱みもある。今はもう、大企業同士の連携では解決できない、超えられない壁があって、日本社会の活性化にはベンチャー、スタートアップの皆さんが欠かせないと思う。4年で400超のスタートアップがエントリーし、リコーと協業してくれたことは、将来の可能性を感じさせる大きな成果だったと思います」

また、挨拶では海老名の「RICOH Future House」の1階に、TRIBUSで実証事業に取り組んでいるチームの内容を展示する「TRIBUS スタジオ」を開設したことも紹介されました。
社内起業家チームのプレゼンテーション
社内起業家チームで、最終審査を通過、TRIBUS推進室に採択されたのは以下の3チームです。
(1) サッカー選手の視界を360°撮影した映像を活用したコーチング用ソリューション
(2) 時間の価値を大切にするオフィスワーカー向けの自分時間マネジメントツール
(3) 事業承継により黒字廃業・諦め廃業をなくすサービス
サッカー選手の視界を360°撮影した映像を活用したコーチング用ソリューション

2月の統合ピッチの後現場視察、ヒアリングなどを重ね、コーチングに比重を置いたサービスでのスタートに変更しています。
「サッカー指導の現場では、状況判断のコーチングに困っているという課題があることが視察をとおして分かったため、この分野でスモールスタートし、技術向上を進めてから、視聴者が選手と視界を共有するようなエンタメに拡大していきたい」(登壇した江口陽介さん)
RICOH THETA、RICOH Remote Fieldなど既存技術をベースにアプリケーションを開発すること、ウェアラブルデバイスとしての装着性の向上を図っていくとしています。
質疑応答では技術面、市場の可能性などに質問が集中し、厳しい意見も多く聞かれたため、江口さんは「落ちると思っていた」そうですが、見事採択されました。山下会長は、授賞時に「いろいろ意見はあったが、これからはスポーツとアートがビジネスの中心に来ると思う。社内外からアドバイスをいただきながら続けていってほしい」とエールを送りました。
時間の価値を大切にするオフィスワーカー向けの自分時間マネジメントツール

個人のスケジュール、タスク管理と、振り返り機能をミックスしたサービスで、「働く」につきまとうちょっとした問題を解決するものだと説明。
「人生の半分の時間を占める『働く』をどうより良くしていくかについて、個人任せになっており、そのサポートがない状況を解消したい。また、働くことに付帯するさまざまなマイクロストレスも解決したい。これは、リコーが掲げる『“はたらく”に歓びを』というミッションにも沿うものだと考えています」(登壇した小笠原広大さん)
2月統合ピッチ以降、社内での試験的導入・検証も実施。94%もの高い利用継続希望があったことから、事業化への手応えを得ていたそうです。
プラン全体はよくリファインされていますが、質疑応答では、サービス内容や対象顧客等の細かな点で質問が相次ぎました。登壇した小笠原さんは、TRIBUSスタート時に事務局メンバーの一人として運営に携わった経験の持ち主で、「ついに“あちら側”に行ってしまったか」とあちこちから祝福の声が上がっていました。
事業承継により黒字廃業・諦め廃業をなくすサービス
全国の中小企業の事業承継をサポートするサービスです。全国で年間5万3426件(※出典:株式会社帝国データバンク 全国企業「休廃業・解散」動向調査(2022年))の中小企業の休廃業があり、そのうち54.3%が黒字廃業。これは2兆3677億円もの経済損失にも相当します。この事業は、こうした黒字廃業、あきらめ廃業をなくすことをミッションにしています。 チームの西本さん、黒川さんの2名はリコージャパン所属。西本さんによると、リコージャパンは付き合いが数十年にもなる“長い”顧客が多いのが特徴で、同じ顧客を長く担当することも多いとか。事業アイデアも、こうした顧客とのコミュニケーションから生まれたそうです。

「4年前に、廃業する顧客から『リコーさんで事業承継をやってくれないか』と相談されたことが直接のきっかけ。リコーの営業マンは、お客様とずっとご一緒しているからお客様の声も聞けるし、お客様にも頼りにしていただける。お客様に恩返しする意味でも、このアイデアは必ず事業化しなければと思った」(登壇した西本崇政さん) 2月の統合ピッチでは、事業を譲りたい事業者と、引き継ぎたい事業者のマッチングサイトという仕組みづくりを発表しましたが、今回のプレゼンではそこから大きく踏み込んだプランを開示。起業家、事業承継希望者の探索や、自治体との連携など、取り組むべき課題は少なくありませんが、山下会長は授賞式で「非常にハードルが高い事業」としつつも、「日本が取り組むべき課題で、やる意義は大きい。ぜひがんばって続けてほしい」と激賞しました。 西本さんも「本当は自治体と企業で協力して取り組んで行く仕事だと思うので、リコーが進んでやっていきたい。」と話しています。 「リコーで営業をやっている人間なら、みんなそう思うと思う。お客様に感謝しているし、恩返しもしたい。これはリコーのDNA。ぜひやりとげたいと考えています」(登壇した西本崇政さん)
スタートアップ企業のプレゼンテーション
後半のスタートアップ企業の発表では、2月の統合ピッチ以降、事業・実証を継続していた5社のうち4社が登壇しました。
Two Gate

Two Gateはロバストで汎用性の高い基幹システムをベースに、エンタメ業界でさまざまなコンテンツ、ソリューションを提供してきた実績がありますが、今回はユニークQR、ユニークURLを使った新しいサービスを提案。これまでとはまったく異なる手順で、新しいコンテンツの提供が可能になります。リコーが持つバリアブル印刷の技術を用いており、協業の意義は非常に強いと言えそうです。2月以降、周辺プロダクトの開発や、飲料メーカーへの共同提案を行うなど、着実にステップアップを重ねています。
質疑応答では、リコー未来デザインセンター所長の駒場瑞穂が、リコーとの協業を進めていることに対し謝意を述べています。
「これまでリコーはラベル印字にしても、レーザーマーカーのダイレクト印刷にしても、表示すべきものを表示するというビジネスをやってきて、それをもっと異なる、セールスプロモーションのようなことに使えないかと模索してきたが、なかなかうまくいかなかった。御社とご一緒することで、そこが突破できる。本当にありがたいことで、引き続き、よろしくお願いしたい」
今後はバリアブル印刷の単価を下げることが主な課題になっていくそうですが、登壇したTwo Gate・小林輝紀さんは、リコーの印刷技術、印刷機導入のライフサイクルも分かったことが大きな成果であり、「急がず、長いスパンで協業を進めたい」と話しています。
Scalar
Scalarは、補助金申請のDX化を実現する「Scalar Self」を提供。2月の統合ピッチまでに、リコージャパンの現場の声を活かしてものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金の2つの補助金申請も扱うことが決定。2月以降の活動で、ものづくり補助金申請はインダストリアル事業部の事業部方針に組み込まれたほか、PP事業部での活用が決定。IT導入補助金については、説明会を実施し、現在トライアル検証活動を実施しています。
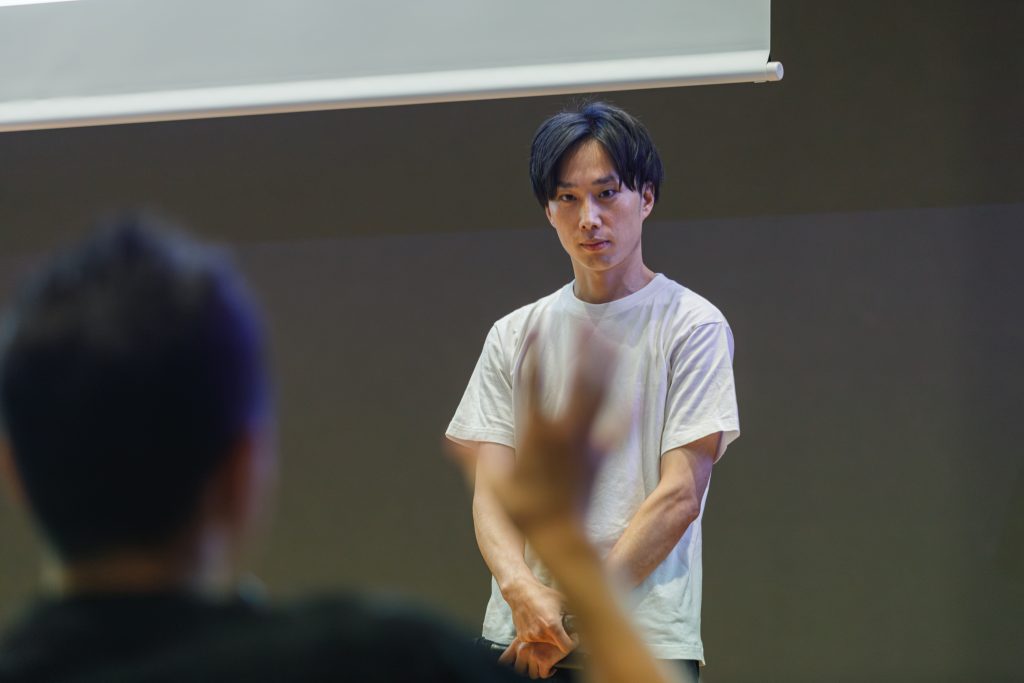
Scalarの特筆すべき点は、補助金申請ソリューションであるにも関わらず、補助金申請をゴールにしていないこと。登壇したScalar・吉田光志さんは、リコージャパンの営業活動でScalarを利用して補助金申請を行い、獲得には至らなかったものの顧客との関係性が強化された事例を示し、「リコージャパンが、Scalarを通しクライアントに寄り添う時間を増やして信頼を獲得すること、これをリコーとの共創として実現したい」と話しています。
同サービスは補助金申請のDXにとどまるものではなく、税金の適正利用や適切な補助金設定などにもつながる可能性を秘めています。社外審査員特別賞の授賞にあたり、Spiral Innovation Partnersの代表パートナー・岡洋氏は「これは上流から使えるシステムを作り、助成金関連のスキームを効率化する可能性のあるもの。社会全体がハッピーになる」と評価しています。
そして、吉田さんはアクセラレーションプログラムへの参加は初めてではあるものの、リコーの雰囲気が「素敵だった」と話しています。
「このようなアクセラに参加するのは初めてでしたが、カタリストのような制度があって、全社を挙げて社内企業やスタートアップを支援・応援する空気、温度感があるのは、他にはないものなのでは。とても素敵な企業だと思いました」
ハイドロヴィーナス

ハイドロヴィーナスは、流体中に生まれるカルマン渦から振り子運動を取り出して発電する技術を開発。メンテナンスフリー、わずかな流量、落差がなくても発電可能などの特徴があり、理論的にはmWレベルからMWレベルまで幅広く対応可能という技術です。アクセラ期間当初は、大規模な潮流発電も視野に入れていましたが、その後データビジネスに軸足を移し、現在は小水力発電用のハードウェアを開発しています。
これは、小さな電力で稼働するセンサー、通信機器を搭載した発電機で、防災に対応するセンシングネットワークを構築できるというもの。登壇したハイドロヴィーナス・上田剛慈さんは、「治水・防災周辺は世間の耳目も集まっており、補助金も大きく動いている。まずはこの治水DXで、さまざまな基盤技術を整え、エネルギー問題に応える大規模発電の事業化を目指していきたい」と話しています。
また、今後は「とにかく早く、販売可能な実機を完成させることが課題」で、センサーや通信機器などさまざまな要素が必要なため、より多くの企業、人材との出会いと協業が必要だとし、TRIBUSこそ、その格好の場であったと振り返ります。
「リコーとご一緒して、とにかく多様な人が集まってくるのが魅力だと感じました。スタートアップはただでさえ人に苦労するので、TRIBUSで多くの人にお引き合わせいただいて、活路を見出すことができたことは一番の成果だったと思います」

FastLabel
FastLabelはAIの効率的なアノテーションを実行するプラットフォームを提供しています。ChatGPTに代表される大規模言語モデル(LLM)や、クリエイティブなアウトプットが可能なジェネレーティブAIなどの登場によって、AIを取り巻く環境は激変し、かつてないほど教師データが増加、アノテーションの重要性が増しています。

「AIにかかる作業の90%がアノテーションと言われるようになった今、人力でアノテーションしていては費用対効果も合わないし、しかしながら放置すれば競争優位性も喪失する。アノテーションの自動化はまさにAIの一番の課題となっています」(FastLabel・上田英介さん)
アクセラ期間中はリコーのニーズ解析とユースケースの構築に取り組み、2月以降はシステム連携の可能性を検討。株式会社リコーデジタル戦略部プラットフォーム推進センター価値創造室とのPoCとして、センターの個別システムで連携を開始しました。AI開発とアノテーションの自動化、学習評価などを一気通貫でできる環境を提供しています。
「私たちはTRIBUSを通じて、リコーさまの『働くに寄り添ったサービス』を実現するだけでなく、リコーさまとともにAIインフラを創造し、日本の企業、産業をもう一度世界レベルに引き上げたいと考えています」
上田さんはそのように話し、連携の継続を強く訴えました。
審査員からの講評と激励
授賞の詳細については一報を御覧ください。ここでは、授賞式の最後に審査員から贈られた講評と激励を紹介します。
 「事業の継続に取り組む方はこれからがスタート。いろいろなところから、サンドバックのようにまず一度打たれてください。一回受けることが大事で、それを消化し、そのうえで行動できるかどうかが、これから発展するための鍵になると思います。考えるだけではダメ。行動を起こすことに期待しています」(Spiral Innovation Partners 代表パートナー 岡洋 氏)
「事業の継続に取り組む方はこれからがスタート。いろいろなところから、サンドバックのようにまず一度打たれてください。一回受けることが大事で、それを消化し、そのうえで行動できるかどうかが、これから発展するための鍵になると思います。考えるだけではダメ。行動を起こすことに期待しています」(Spiral Innovation Partners 代表パートナー 岡洋 氏)

「今回のプレゼンを聞いて、(2月からの比較で)非常に高い変化率を感じました。これは、この変化率を維持すれば、非常に大きな事業になる可能性があるということ。期間をおいて、また皆さんのお話を伺うのを楽しみにしています」(ゼロイチキャピタル 代表パートナー 種市亮 氏)

「一社一社、一人ひとりの熱量がとても高く、そしてまた、社会的意義のある事業ばかりで、私にとっても有意義な一時となりました。リコーさんのリソースは非常に有用ですし、それを使って何ができるかという着眼点はもちろん重要ですが、やはり社会課題ドリブンの視点を大事にしてほしいと思います。それが、事業を大きくしていくときのポイントのひとつになると思います。また、まだエントリーしていない皆さんも、日々の業務の中、お客様との会話の中から、小さな課題を見つけるよう心がけてみてください。それが事業の種になる可能性を秘めていると思います」(マネックスベンチャーズ株式会社 シニアインベストマネジメントマネジャー 永井優美 氏)

「社内起業家チームの皆さん、今日がスタートですが、ピボット、つまり事業が変わっていくことを恐れないでください。次にお会いしたときに、まったく違う事業をやっていたって全然構わない。むしろ2回くらいピボット(*路線変更)したほうが、収益がアップするなんてこともあるくらい。日本、特に大企業の中でやっていると、ピボットしちゃいけないと思いがちですが、自分の首を締めることになってしまいます。また、社会課題解決も大事ですが、マネタイズも重要。そこも忘れずに、身近なところから『なぜ?』という問いを忘れずに、大きな事業に育ててください」(Global Catalyst Partners Japan マネージングディレクター 平出亮 氏)

「イノベーションは、ある一人の長期的な熱量や、空気を読まずに進んでいく力などが、周りを巻き込み、壁を突破していくことで実現していると感じています。それを実行するには、まず『語る』ことが大事。自分がやりたいことをいろいろな人に語ると、絶対にああだこうだと言われます。その中から本質的なものを取捨選択し、アクションしていけば、きっと扉が開いて、大きな価値につながると思います」(株式会社ANOBAKA パートナー 萩谷聡 氏)
ほか、社内審査員を務めた駒場(未来デザインセンター所長)、山田(先端技術研究所 所長)からも、参加チームへの謝意とさらなる活動への呼びかけがありました。そして最後は会長の山下からの言葉で締めくくられました。
「参加した皆さんは、TRIBUSを通じて、事業を成長させることができたと思いますが、同時に、相当個人も成長させることができたのではないでしょうか。
また、このTRIBUSも成長させないといけない。コロナを超えてリアル開催に戻りましたが、さらに工夫を重ねて、もっと社員が参加しやすい、そしてチャレンジする人がもっと力を発揮できるようにしていかないといけないなと思いました。事業はピボットしなければならないというお話がありましたが、TRIBUSもピボットを繰り返し、進化させていきたいと考えています」

事務局リーダーの森久泰二郎は、取材に答えて2022年TRIBUSは「オンライン・オフラインの魅力が相互に引き出せたこと」「さらに多様なエントリーが増えたこと」の2点が特徴であったと振り返っています。
「社内からは面白いところがどんどん出てきますし、スタートアップさんの事業部との連携もどんどん進んできている。TRIBUSが社内に浸透してきているからこそ起こっていることだし、そこが魅力のひとつになっていると思います。
社内チームについてはファイナル4チームとも非常に個性的。販売系もあればハード系もあった。福岡からバリバリのエンジニア集団がエントリーしてきたりもしている。TRIBUSはこうすれば採択される、というような攻略法があるようなものじゃないということかもしれません。だから、これからもどんどん面白いものが出てくるのではと期待しています。
あと、オフラインがやっぱりいいなと感じました。直接会って言葉を交わすことができるのは、関係性強化や今後の発展を考えると必須。その一方でオンラインだからこそ、福岡や岡山など地方からのエントリーが可能になっています。オンラインで間口を広げ、オフラインで深いコミュニケーションを取るという、良い効果を確認できたのが、2022年のTRIBUSだったように思います」
2023年のTRIBUSは、すでにスタートしています。社内起業家の募集は終了しており、8月3日には最初の社内ピッチが開催されました。今後の動向にもぜひご注目ください。
PHOTOGRAPHS BY UKYO KOREEDA TEXT BY Toshiyuki TSUCHIYA
