「TRIBUS 2024」の成果発表会「TRIBUS Investors Day」開催レポート<Part 2:スタートアップ企業編>

2025年2月7日(金)、事業創出・共創を目指す社内外統合型のアクセラレータープログラム「TRIBUS 2024」の成果発表会「TRIBUS Investors Day」が株式会社リコー本社で開催されました。昨年9月の統合ピッチで採択された社内起業家5チームは事業化活動の継続を賭けた発表を、リコー各事業部との連携・実証実験を進めてきたスタートアップ企業9社は、その後の成果を発表しました。レポート<Part2>では、スタートアップ企業9チームによるピッチの内容をご紹介します。応募総数172社の中から選び抜かれた9社が登壇し、アクセラレーター期間中の共創活動の成果を発表しました。
スタートアップ企業のプレゼンテーション
※以下、事業概要/所属/代表者名の順
1. 「AI社長」社長と従業員の距離を近づけ、従業員が自走できるようにする最先端AIサービス
株式会社THA(https://tha-inc.com/) 西山朝子

「AI社長」は、社長の代わりを務めるものではなく、社長と従業員の距離を縮め、従業員が自律的に行動できるよう支援する最先端のAIサービスです。 「日本を支える勇者たちに、最強の強化魔法を」というビジョンのもと、日本の地場の中小企業を主なターゲットとして活動しています。
今回のアクセラレーター期間では、「営業」と「開発」の2軸でプロジェクトを進行しました。営業面では、リコージャパンおよびその強力な顧客基盤を活用し、広い市場での販売検証を実施。開発面では、リコーが有する高度な技術を取り入れ、AI社長のさらなる機能強化を図りました。
営業活動の中では、実際にお客様にもご提案を行い、AI社長への関心をきっかけに、IoT機能や老朽化したサーバーの更新をリコーに依頼したいという声も寄せられました。これにより、単なるAI導入にとどまらず、リコーとの協業を通じて、中小企業全体のDX支援へとつながる可能性が見えてきたとのことです。
協業の第一歩として、今回の共創活動をきっかけに少なくともチームビルディングの段階に踏み出せたと語る西山氏は、 「日本中の中小企業の皆さまに対して、これまで以上に“技術という名の最強の強化魔法”を共に届けられるような、そんなチームをつくっていきたいと考えています」 と力強く締めくくりました。
2. LLM活用で超ローカルな情報を自動で配信。推しを見つけてその地域ならではのスポットを見つけるアプリ「SpotsNinja」
イオリア株式会社(https://aeolia.co.jp/) 松原 元気

イオリア株式会社は、ユーザーから半径1キロのよりディープな情報を届けるハイパークラシファイドメディア「SpotsNinja(https://spotsninja.com/)」を提供しています。
今回の検証活動では、ターゲットユーザーの明確化、法人ニーズのヒアリング、ビジネスモデルの構築、技術的な検証の実施の4点に取り組みました。
まず、1点目のターゲットユーザーの明確化については、リコーの伴走社員である「カタリスト」の協力のもと、特に地方在住の若年層約20名にヒアリングを実施。その結果、地方在住の30歳前後の主婦層をターゲットとして特定することができました。
2点目の法人ニーズのヒアリングに関しては、エンジニアのみで構成された同社にとって初の営業活動でしたが、リコー営業部門の支援により、企業との対話の機会を得て、実際のニーズを把握することができました。
3点目のビジネスモデルの構築では、ターゲットユーザーと法人ニーズの解像度を高めることで、具体的なモデルの検討・構築に着手することができました。
4点目の技術面では、リコーの音響通信技術を活用したスポーツビジネスでのテクノロジー活用やSpotsNinjaとスポーツビジネスの可能性の検証し、今後の展開に向けた技術的な裏付けを進めています。
最後に松原氏は、「人から愛される事業をつくれるよう、これからも頑張っていきます」と力強く締めくくりました。
3. 『連携ジョシュ』医療介護領域の人とケアをつなぐ情報連携クラウドサービス
株式会社ジョシ(https://zyoshu.co.jp/) 山﨑 康平

株式会社ジョシュは、医療・介護における情報連携サービスを提供しており、医療・介護従事者が誇りを持って、患者本人や家族とともにケアを築いていける世界の実現を目指しています。現在の医療・介護現場では、依然として多くのアナログ業務に時間を奪われており、これが大きな課題となっています。
今回の検証期間では、サービスを「どう拡げるか」「どう拡がるか」の両面からアプローチしました。
「どう拡げるか」については、現場のニーズを確認した結果、リコーの複合機との連携をはじめ、さまざまな技術との連携の可能性があると明らかになりました。また「どう拡がるか」に関しては、リコージャパンの熊本・奈良支社の営業担当とともに現場ヒアリングを実施。その中で、顧客から非常に好意的な反応が得られ、確かな手応えを感じたといいます。
すでにリコージャパン熊本支社において販売面での連携が決定しており、活動を通じてリコーの営業力の強さを実感したと語る山﨑氏は、現場同行の中で「愛される営業マン」という価値にも触れ、大きな学びを得たとのことです。
山﨑氏は最後に、「TRIBUSの期間、本当に使い倒させていただきました。何よりも良かったのは、リコーのアセットや、リコーの皆さんを通じて、リコーという存在そのものを“愛せた”ことだと感じています」と感謝の気持ちを込めて締めくくりました。
4. RICOH kintone plusとのワークフロー承認・経費清算連携等を伴う出張・ワークスペース・会議室・弁当などの法人購買・手配等連携によるさよなら雑務
株式会社エイチ(https://eichiii.co.jp/) 伏見 匡矩

株式会社エイチは、「さよなら雑務」を掲げ、人が人らしく、本来取り組むべき仕事に集中できる社会の実現を目指しています。同社が展開する統合型BPaas×AIプラットフォーム「Eichiii」は、ワークフロー承認や経費精算などの業務を効率化・削減することで、生産的な時間を生み出す統合型BtoB業務プラットフォームです。
現在、各種手配および経費発生における事後処理のフローにはすでに対応できている一方、事前フローには課題が残っており、リコーの「RICOH kintone plus」との連携によってその課題の解決を図ろうとしています。
検証期間中には30社以上からニーズを確認し、特に売上規模50~300億円の企業層において高い需要があることが判明しました。
こうした結果を受けて伏見氏は、「リコーと連携して、ONE JAPANで雑務をなくす。このコンセプトを、私は世界に届けたいと思っています!」と情熱を込めて発表を締めくくりました。
5. デジタルARマップで地域の魅力を拡張!観光客の周遊促進と多言語ガイドを実現し、交流人口を拡大へ
株式会社palan(https://palan.co.jp/) 齋藤 瑛史

株式会社palanは、誰でも手軽にARコンテンツを作成できるサービス「palanAR」を提供しています。今回の共創は、「デジタルARマップで地域の魅力を拡張!」というテーマで応募し、検証を行ってきました。
同社は、キラーユースケースの具体化と拡大を課題として捉え、その解決を目指して活動を進めてきました。初期段階ではヒアリングを行い、地域が産業創出を求めていることや、防災分野での活用、さらにはインバウンド観光客向けのニーズなど、多様な可能性を発見しました。
その後、リコーの360度カメラ「THETA」との連携を模索するため、THETAを活用したイベントを開催し、参加者からは90%という高い顧客満足度を獲得しました。
また、国内外の展示会にも出展し、現在は海外の企業や自治体との交渉も進行中とのことです。観光や防災分野のニーズについては、すでに5つ以上の自治体に提案を行っており、着実に成果を上げています。
今後の展望について齋藤氏は、「私たちのAR技術と、リコーのネットワークを組み合わせ、この4カ月で得られたニーズをもとに、ARを通じて地域社会の価値をさらに高めていきたい。そして地域を活性できる未来を実現したいと思ってます。」と語り、発表を終えました。
6. オフィス、シェアオフィスの資源循環を実現するリユーザブルカップシェアサービス“Circloop”
株式会社Circloop(https://circloop.jp/) 中村 周太

株式会社Circloopは、「サステナビリティをあたりまえにする」ことを目指し、リユーザブルカップのシェアリングサービスを開発しています。
今回のTRIBUSでは、実証プログラム期間中に1件の実証と2件の検討を進めました。
まず実証では、実際に稼働中のシェアオフィス内のカップ返却スタンドにリコーのデジタルサイネージを設置し、環境意識の変化を促進する取り組みを実施。働く人々のサステナビリティ意識を高める資源循環ソリューションとしての可能性を探りました。アンケート結果からも一定の意識変化が確認され、今後はサイネージを含むデジタルの活用を軸に取り組みを広げていきたいと中村氏は語りました。
検討の1件目は、リユーザブルカップの再生材活用に関するものです。リコーの複合機に使用される再生材や、昨年度TRIBUS採択企業である株式会社amuが取り組む廃漁具の再活用についてヒアリングを行い、6月を目途に成果を出すべく検討を継続中です。
また、TRIBUS 2021採択企業の株式会社スマートショッピング(現:株式会社エスマット)が開発したIoT重量計「スマートマット」を用いた重量計測による回収サイクルの可視化や、カメラ技術によるカップの汚れ検知の仕組みについても、ロードマップを策定予定とのことです。
最後に中村氏は、「このサービスを利用してくださっている企業の皆さん、そして現場で実際に使っている皆さんこそが、資源循環の先駆者であり、いわばヒーローやヒロインだと考えています。そうしたメッセージをしっかりと伝え、資源循環の輪をさらに広げていきたい」と締めくくりました。
7. プライバシー保護×データ活用技術で、働く人を守り、寄り添い、自律を支援する新規プロダクトを開発
EAGLYS株式会社(https://eaglys.co.jp/) 阿須間 麗

EAGLYS株式会社は、データを暗号化したまま分析できる「秘密計算」技術の研究開発を行っています。今回のTRIBUSでは、リコーと共に「働く人の自律を支援する新規サービスの創出」という同社における新規事業にあたるテーマの検討に挑戦しました。
アクセラレーター期間中は、当該領域での事業化に向けて、「プロダクトで解決すべき人事課題は何か」、そして「プライバシー保護技術がどのように活用できるのか」の2点を中心に検証を進めました。
冒頭、阿須間氏は「個人とチームの気持ち、心をコアにした組織を作る。そんな世界観を私たちのプロダクトを通じて実現したいと考えています」と力強く語りました。
現在、ピープルデータの活用には多くの人手が必要とされており、データの収集や活用まで至らないケースが多く見受けられます。さらに、データ化のためには高い言語化・文章化スキルが求められるほか、頻繁な更新が難しく、情報がすぐに古くなってしまうといった課題も存在しています。
これらの課題を解決するために着目したのが、「個人の活動情報」です。これは、日々の業務やプライベートにおける行動を記録したログデータであり、センサー等によって取得されるデータも含まれます。
リコーのセンシング技術により取得したデータを、EAGLYSの秘密計算技術によって秘匿化し、安全に活用することで、個人と組織をより高い解像度で理解できるようになると阿須間氏は語ります。
今後は、「エバンジェリストユーザー」と呼ばれる協力者と共に、実際のユースケースデータを用いたさらなるソリューション仮説の検証を進めていく予定です。
8. 樹脂判別ハンディセンサーと統計的データ解析による、プラスチックごみの価値の自動計算アプリの開発
株式会社 a.s.ist(https://www.a-s-ist.com/) 林 悠偉

株式会社 a.s.istは、ベイズ理論やスパースモデリングといった先端的なデータ解析技術を活用し、企業の課題解決を支援しています。今回のTRIBUSでは、リコーの樹脂判別ハンディーセンサーにおけるプラスチック判別機能の改善に加え、リコーグループ内の複数部署へのヒアリングを通じて、データ解析技術による課題解決の可能性を検証しました。
発表の冒頭、林氏は「統計的AIが切り開くデータ解析の自動化、専門知識不要の次世代ツール」と題し、プレゼンテーションを開始しました。
今回の検証では主に、以下の2点に取り組みました。
1つ目は、樹脂判別ハンディーセンサーの判別の自動化です。このセンサーは、製造業や廃棄物処理業向けに販売されており、プラスチックの種類を迅速に判別できます。ただし、従来は樹脂が単層構造なのか複層構造なのかを事前に知っていなければ正確な判別ができないという課題がありました。これに対し、同社は単層・複層を自動判別するアルゴリズムを開発し、この課題を解決しました。
2つ目は、リコーの各事業部門における材料合成後の特性評価作業に関するものです。評価項目は属人性が高く、評価作業には多くの時間がかかることが課題でした。これを実験データの自動解析により効率化し、検証を行いました。
最後に林氏は、「今後のa.s.istは、今回のTRIBUSで得られた知見を活かし、計測機器へのアルゴリズム導入や自動データ解析ソフトウェアの開発・検証を通じて、製造業の自動化と進化を牽引してまいります」と今後の展望を語りました。
9. 「それ本物?」トレーディングカードのAI真贋鑑定サービス「VALUE SCOUTER SERVICE(VSS鑑定)」
株式会社コレクテスト(https://www.collectest.com/) 岩田 翼
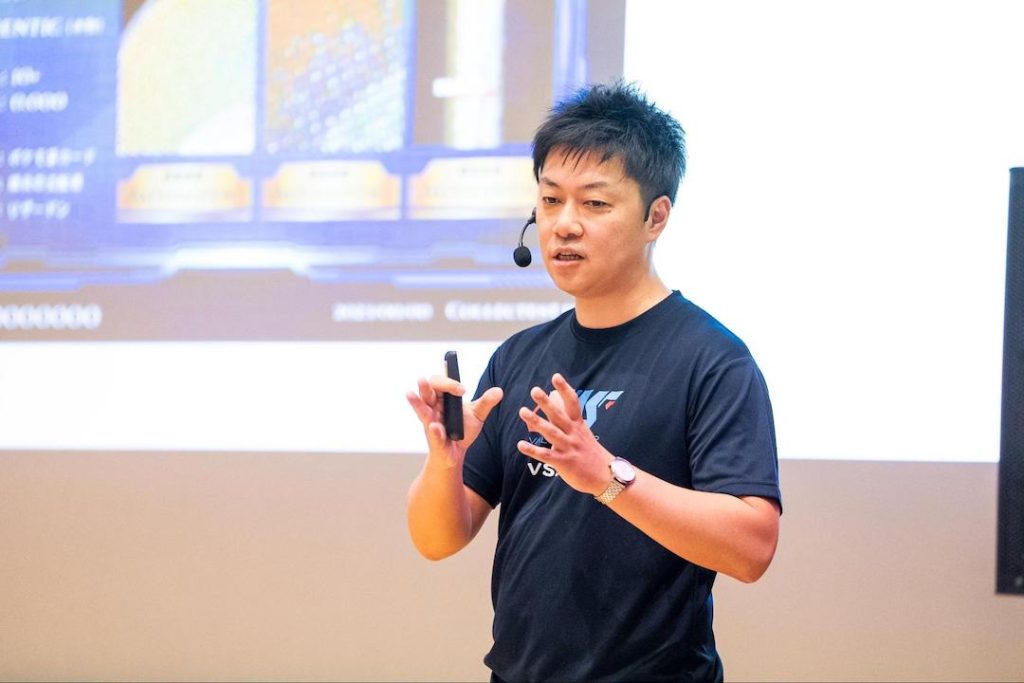
株式会社コレクテストは、トレーディングカードのAIによる真贋判定と状態判別グレーディングを行う企業です。日本のトレーディングカード業界では、国内での鑑定が困難であったり、鑑定基準が公開されていなかったり、価格が不透明であるといった課題が長らく存在しており、同社はこれらの課題解決を目的として創業されました。
すでに、日本国内での鑑定、鑑定基準の整備、価格の透明化については一定の成果をあげているものの、中古市場での価格決定に大きく影響する「グレーディング」については、依然として人の目による対応が必要であり、AI化が進んでいないという課題がありました。
今回のTRIBUSでは、リコーグループと連携し、「現代の美術品」とも称されるトレーディングカードに対するキズのAI自動判別の検証を実施しました。
検証期間中は、カード表面のダメージやキズを可視化し、AIで自動判別する技術の構築に取り組みました。初期の検証では、人の目で確認できる範囲のキズは十分に検出可能であることが示され、さらに人の目では見つけにくい微細なキズや修復跡までも検出できることが確認されました。また、価格に影響する重要なダメージのみを抽出するための最適な撮影手法も確立しています。
ビジネスモデルの検証では、トレーディングカードショップを訪問し、現場でのヒアリングを実施。その結果、多くの店舗が人手不足や作業工数の多さに課題を感じており、AIグレーディング技術の導入に対して高い関心と導入意欲があることが明らかになりました。
今後は海外やトレーディングカード以外にも挑戦したいと語った岩田氏。最後は「今回の検討をきっかけに、ぜひ今後とも継続的に連携するというこのチャンスを掴みたいと思ってます。」と熱く締めくくりました。
審査員コメント

審査員の株式会社リコー CTO 野水泰之氏は、今回成果発表したスタートアップ企業に向けて次のようにメッセージを送りました。
「最初の1~2回に参加して以来、しばらく間が空いてしまっていたのですが、今回久しぶりに審査員として参加して、改めて全体のレベルが格段に上がっていると強く感じました。
また、私は常々『イノベーションは、異なるもの同士がぶつかり合うことで生まれる」と考えていますが、そこにもうひとつ、“熱量”が加わらないと真のイノベーションにはならないのではないかと以前から感じていました。今回の発表を見て、その考えに確信を持つことができました。
そうしたイノベーションが生まれた瞬間に、私たちが少しスパイスを加えたり、火をかけたりして育てていくことが大切なのだと感じました。
スタートアップの皆さんのお話を聞いていて、その熱量と『これで行くんだ」という強い意志に圧倒されました。本当にすごいと思います。
同時に、皆さんの取り組みに対して、『ここにこういったスパイスを加えたらもっと良くなるのでは?」という視点も生まれましたので、今後、そういった場面でお手伝いできれば嬉しいです。
個人的には、今回、社外審査員の皆さんと直接お話しできたことも非常に貴重な経験でした。さまざまな視点から学ばせていただき、今後の審査にも大いに活かしたいと思います。
皆さん、本当にお疲れ様でした。ここからが本番です。ぜひ、一緒に頑張っていきましょう。改めて、ありがとうございました。」
