今年のテーマは「好奇心を持って未知の世界に冒険する」。「TRIBUS2024」統合ピッチレポート<Part 2>

Part2では、社外スタートアップ企業13社のピッチ内容をご紹介します。社外スタートアップ企業は、以下の5つの事業領域+その他の領域に関連したビジネスアイデアの募集に応じた172社の中から書類審査、面接を経て選び抜かれた企業です。
(1)ビジネスコミュニケーションスキルを向上させるAIトレーニングシステム
(2)ワーカーのセルフマネジメントを支援する持続的なUXグロースサイクル
(3)プラスチック資源循環による共創ソリューション
(4)デジタルの力で交流人口創出・拡大につなげ、地域活性化を実現
(5)PFUの技術を活かした”はたらく”を変えるに貢献する新たな事業の共創
(6)リコーアセットを活用した自由なテーマでの募集
いずれも自社とリコーグループが持つアセットを組み合わせることで、ビジネスのステップアップを目指しています。それぞれのピッチの概要を紹介していきます。
社外スタートアップ企業
※以下、事業概要/会社名/登壇者名の順
1.「AI社長」社長と従業員の距離を近づけ、従業員が自走できるようにする最先端AIサービス
株式会社THA 西山朝子

西山氏は冒頭、自身の事業について「日本中の中小企業の社長を強化することを目指して活動している会社です」と紹介しました。
中小企業をターゲットとしている理由について、西山氏は「日本の経済は大部分を中小企業が担っているものの、AIの活用がなかなか進んでいない業界です」と説明しました。中小企業には生産性の低さや人材不足、事業承継といった様々な課題が山積しています。その要因の一つとして、西山氏は多くの中小企業が社長依存の組織体制であることを挙げました。しかし、実際に社長のスケジュールを見ると、朝から晩まで、土日も含めてびっしりと予定が詰まっており、スマホの通知の数も膨大です。西山氏は、こうした方々に向けてサービスを提供したいという思いで活動しています。
「AI社長」は、社長の代わりを作るのではなく、社長と従業員の距離を近づけ、従業員が自走できるようにする最先端のAIサービスです。最後に西山氏は、「リコーの中小企業向け顧客基盤と技術力を活かしながら、マーケットでの販売検証やプロダクトのアップデートの可能性を共に見ていきたい」とトライバスへの期待を語り、発表を締めくくりました。
2.『連携ジョシュ』医療介護領域の人とケアをつなぐ情報連携クラウドサービス
株式会社ジョシュ 山﨑 康平

株式会社ジョシュは、医療介護の情報連携サービスを提供しており、医療介護従事者の方々が誇りを持って、本人や家族と共にケアを作り上げていく世界の実現を目指しています。
医療介護従事者は、実際のケアに加え、多くの間接業務にも時間を費やしています。同社は、情報連携の質と量を向上させることでケアの質や効率を高め、まるで「助手」のように医療介護の業務全体をコーディネートしていきます。特に、アナログなやり取りとデジタル化が混在している現状を考慮し、それらをつなぎ合わせるハブの役割を果たしていきます。
アクセラレーション期間中は、さらなるサービス向上のために、医療介護事業所で多用される複合機を起点とした情報連携の可能性を模索しています。また、リコーの請求書業務効率化クラウドサービスであるMakeLeapsとの連携や、医療介護領域のニーズをさらに深掘りしていくことを検討しています。
最後に山﨑氏は「医療介護事業者がケアに集中できる環境を作るため、ぜひ共創させていただければと思っています」と審査員に向けて力強く訴えかけました。
3.RICOH kintone plusとのワークフロー承認・経費清算連携等を伴う出張・ワークスペース・会議室・弁当などの法人購買・手配等連携によるさよなら雑務
株式会社エイチ 伏見 匡矩

株式会社エイチの伏見氏は、「さよなら雑務」をテーマに掲げ、人が人らしく、本来の仕事に集中できる社会を実現したいと力強く訴えました。また、「リコーも同じ思いを抱いているのではないでしょうか」と問いかけながら発表を始めました。
まだ多くの顧客が抱える雑務を解決したいと語る伏見氏。「皆さん、出張をイメージしてください」と切り出し、次のように話を続けました。「規程を確認し、事前に申請し、楽天トラベルで価格を調べ、申請して承認され、また購入し、出張後は経費のレシートをまとめ、写真を撮って経理に送る。そして、経理が処理をして給与に反映する。この一回の出張のために、何をやっているんだと思いませんか?」と、雑務の多さを指摘。同社はこれらの煩雑な業務をワンストップで解決できるとし、RICOH kintone plusとの共創を目指していることを強調しました。これにより、法人顧客の獲得や顧客価値の最大化が図れると自信を持って語りました。
最後に伏見氏は、「通過した暁には、システムの検証、営業チームとの連携、各種サービスとの連携、販売代理の体制構築を行い、世界を一緒にリードしていきたい」と情熱的に締めくくりました。
4.相談内容を対話形式でリアルタイムに回答するAIサービス「Hanaso」
株式会社One StepS 田山 凌汰
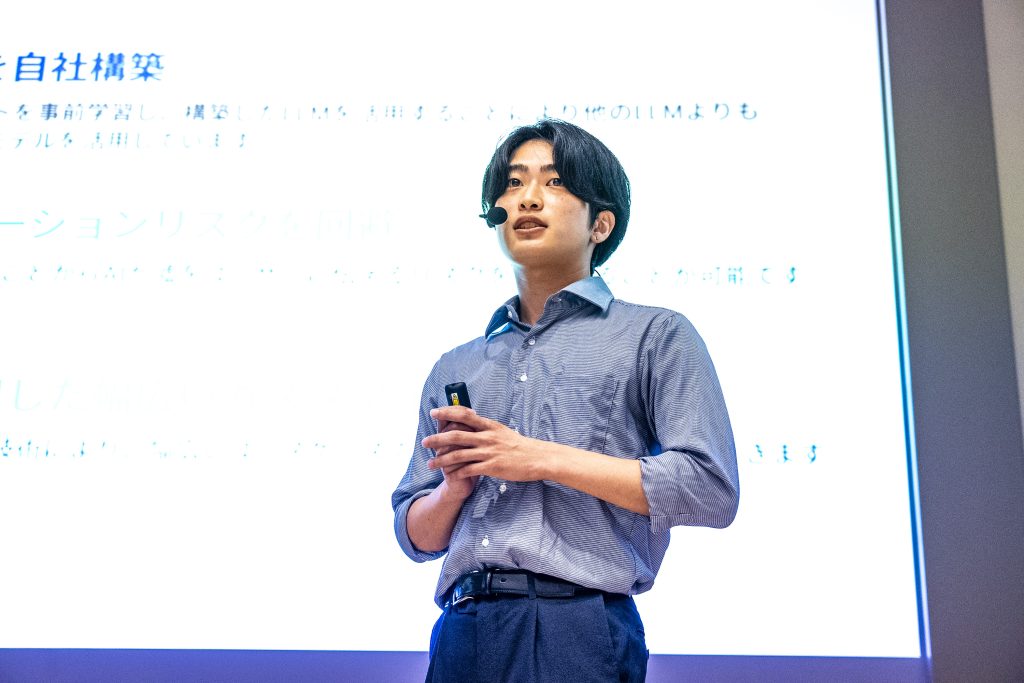
株式会社One StepSは「デジタルを通じて社会とユーザーの繋ぎ目を作る」というミッションを掲げ、生成AIの導入支援や開発サポートを行ってきました。今回、同社がTRIBUSで目指すのは、相談内容に対して対話形式でリアルタイムに回答し、対話コストを削減するサービス「Hanaso」での共創です。
「Hanaso」は独自のデータセットでカスタマイズが可能で、AIの誤答(ハルシネーション)のリスクを最小限に抑える技術を活用しています。この技術により「Hanaso」は既に多くの企業で導入が進んでいます。今回の共創では、この技術を活用し「対話型トレーニングシステム」の開発を目指しています。AIがロールプレイングを実施し、その際のコミュニケーションを解析した後、対話型AIを使ってフィードバックを行います。対話型AIに強みを持つOne StepSと、センシング技術を持つリコーが協力し、従業員の充実感や満足度を向上させ、組織全体の力を引き上げることが目的です。
最後に田山氏は、「弊社の『Hanaso』を活用し、ビジネスシーンでのOJTを支援することで、個々のビジネススキルを向上させ、最終的には組織の力や売上向上を実現し、両社でこのプロダクトを販売していく未来を考えています」と、協業への期待を語り発表を締めくくりました。
5.ビジネスコミュニケーションにおけるAIトレーニングシステム
株式会社エムニ 下野祐太

下野氏は冒頭で、自社を「生まれたばかりの会社」と紹介し、京都大学発のスタートアップであり、松尾研(技術顧問に東京大学の松尾豊教授)の技術力を強みとしていることをアピールしました。
同氏がアクセラレータプログラムに応募した理由は、リコーとのミッションの類似性、親和性が大きな要因であったといいます。同社は「AIで働く環境を幸せに、世界にワクワクを」というミッションを掲げており、リコーのAIなどのデジタルサービスで、企業理念の使命と目指す姿と定める「“はたらく”に歓びを」というミッションと方向性が一致していることから、協業を通じて同じ目標に向かって進めると考え、応募に至ったとのことです。
下野氏は、エンゲージメント向上を目的とするAIコミュニケーションシステムの開発を、リコーの音声合成AIと自社の動画生成技術のコラボレーションによって実現できると考えています。最後に、「弊社と御社で密に連携しながら開発を進めたいです。このトレーニングシステムを共創することで、コミュニケーションスキルの向上を図り、リコーのミッションである『“はたらく”に歓びを』、そして我々の『働く環境を幸せにする』というミッションを共に達成していきたいと思っています」と、働く環境の改善に対する強い思いを語り、発表を締めくくりました。
6.プライバシー保護×データ活用技術で、働く人を守り、寄り添い、自律を支援する新規プロダクトを開発
EAGLYS株式会社 阿須間 麗

EAGLYS株式会社は、データを暗号化したまま分析できる「秘密計算」技術の研究開発を行っています。今回のTRIBUS挑戦では、リコーと共に「働く人の自立を支援する新規サービスの創出」というテーマに挑戦したいと考えています。
この技術は、強固なセキュリティによりプライバシーを保護しつつ、機密性の高いデータを安全に活用できる点が特徴です。たとえば、企業間で社外秘の情報を暗号化したまま共有・活用するコラボレーションや、従業員のセンシティブな個人データを安全に分析することで、組織と従業員の相互理解を深めることが可能です。
阿須間氏は、働く人を支援し、自律型人材の育成やパフォーマンス向上、離職率の低減といった企業側のメリットに繋がるサービスやプロダクトを目指していると語りました。
アクセラレーション期間では、独自の提供価値や共創ならではの付加価値を明確にすること、サービスに必要な機能やユーザー体験(UX)、さらにはプライバシーに配慮しつつ有用なデータの活用方法を明らかにしていきたいと考えています。
また、ユーザーが「使ってみたくなる」「積極的に使いたくなる」ような体験をどのように提供するかが、重要な検証ポイントになると述べました。さらに、事業化に向けてはビジネスモデルやシステムの概要設計を具体化していきたいとの考えも示し、発表を締めくくりました。
7.内省の習慣化をサポートするWEBアプリ「リフクラ」
株式会社TIELEC 隆祐人

株式会社TIELECは、生体情報とAIを融合させた次世代カウンセリング・コーチングシステム「リフクラ」を提供しています。
同社の隆氏は、エンジニアとして働いていた際に約3ヶ月の休職を経験し、自分の内面と向き合うことの重要性に気づきました。しかし、その過程は決して簡単ではなく、仕組み化されていない部分が多いと感じたことが起業のきっかけとなったと語ります。
日本では「プレゼンティーイズム(疾病就業)」が大きな課題となっており、企業における健康関連コストの中で、年間19兆円もの損失が生まれているとされています。また、就業者の90%がストレスを抱えており、過半数がうつ病の初期症状を経験しているという深刻な現状があります。今回のTRIBUSで、隆氏はAIと生体情報を融合させた次世代のカウンセリング・コーチングシステムをリコーとの共創で実現したいと述べました。
発表の最後に、隆氏は次のように締めくくりました。「想像してみてください。あなたの隣に24時間365日、最高のコーチが寄り添う世界を。私たちはAIと生体情報の力でその世界を現実にしようとしています。一人ひとりが自分を深く理解し、継続的に成長できる社会を目指しています。その社会では、個人の自己実現と組織の生産性が見事に調和するでしょう。これは単なる夢物語ではありません。リコーとTIELECの技術を融合し、働く人々の幸せと企業の成功を両立する新しい時代を切り開きましょう。」
8.樹脂判別ハンディセンサーと統計的データ解析による、プラスチックごみの価値の自動計算アプリの開発
株式会社 a.s.ist 林 悠偉

「私たちはリコー様と共に、最先端のデータ解析を活用してプラスチックリサイクルの最適化に取り組みます。」と林氏は発表を開始しました。
廃棄物を原料として新たな製品を作る、環境負荷の少ないリサイクルは「マテリアルリサイクル」と呼ばれます。しかし現代社会では、プラスチック廃棄物にはさまざまな種類のごみが混在していたり、汚れていたりするため、これをリサイクルするには種類ごとの分別と洗浄が必要です。このプロセスはコストが非常に高く、リサイクルの採算が取れないという課題があります。その結果、日本国内ではマテリアルリサイクルの実施率は2割程度にとどまっており、まだまだ改善の余地があります。
これらの課題解決に向けて、今回の共創活動では、リコーの樹脂判別ハンディセンサーで得られた計測データに対して、自社の統計理論を応用した最先端のデータ解析技術を適用し、プラスチックごみの自動価値計算ソフトウェアの開発を目指します。
林氏は最後に、「弊社のメンバーは全員、現在も東京大学の博士課程で最先端の研究を行っており、世界的にも評価を受けています。大規模な実験施設であるSPring-8や、東京大学物性研究所で招待講演を行うなど、私たちの技術力には自信があります。」と述べ、共創への強い意欲を表明しました。
9.オフィス、シェアオフィスの資源循環を実現するリユーザブルカップシェアサービス“Circloop”
株式会社Circloop 中村 周太

株式会社Circloopは、「サステナビリティをあたりまえ」にするためのリーズナブルカップのシェアリングサービスを開発しています。
中村氏は「容器包装はほとんど循環されておらず、廃棄されています。しかし、世界的な流れは廃棄を減らし、環境に配慮した方向に向かっていると感じています。」と、日本の資源循環に関する課題を指摘し、ヨーロッパにおける先進的な対策についても説明しました。
Circloopのサービスでは、カップの洗浄、配送、回収をフルサービスで行います。ユーザーはカップを手に取り、飲み終わったら返すだけで、資源循環や環境負荷削減への貢献が可能になります。共創を通じて、例えばオフィスで使用したカップを駅で帰り際に返却したり、サッカー観戦後に最寄りのカフェで返すといった、「どこでも使えて、どこでも返せる」サービスの実現を目指しています。検証では、「リコーのデジタルサイネージを活用し、リユースの枠を超えて、働く人々のサステナビリティ意識を高める資源循環ソリューションを作りたい。さらに、ハンディーセンサーなどを活用し、日本のリユースシステムを共に前進させていきたい」という考えも示しました。
10.デジタルARマップで地域の魅力を拡張!観光客の周遊促進と多言語ガイドを実現し、交流人口を拡大へ
株式会社palan 齋藤 瑛史

齋藤氏は「AR×AI×デジタルマップによる地域活性化の共創提案」と題して発表を開始しました。
同社が提案するのは、デジタル技術を活用した持続可能な観光体験です。現在、地方の観光地では観光客が増加している一方で、オーバーツーリズムや外国人観光客への言語対応、回遊データの活用といった課題があります。これらの課題に対して、デジタルマップやARコンテンツ体験を活用することで、観光体験の質を向上させることが可能だと述べました。
リコーとの提携においては、IT技術や地方ネットワークの強み、デバイスやソリューションの活用を目指しています。また、中期的にはARグラス、長期的には製造業や医療現場など、多様な業界へのバーティカル展開を視野に入れています。
さらに、齋藤氏は「最終的には、ARデバイスや私たちの持つセンシング位置情報データを活用し、キラーユースケースとなるようなARグラスを共同開発できればと考えています。」と、今後の展望を語り、発表を締めくくりました。
11.LLM活用で超ローカルな情報を自動で配信。推しを見つけてその地域ならではのスポットを見つけるアプリ
イオリア株式会社 松原 元気

イオリア株式会社は、ユーザーから半径1キロのよりディープな情報を届けるハイパーローカルソーシャルメディア「SpotsNinja」を提供しています。
松原氏は、WEB上やSNSなどから収集した情報をLLMを使って構造化データとして独自のデータベースに落とし込み、マップに反映させることで、日本中の様々なローカルでディープな情報を配信できると語りました。LLMと位置情報を活用しユーザーごとに最適な情報体験を提供していきたいとしています。これまでに様々なメディアや企業からオファーを受ける中で、「位置情報の活用やマップの音声紹介機能が欲しい」といった声があり、リコーとの共創を考えるに至ったと述べました。
現在はWEB版を広島県のみで提供しており、リリース1ヶ月で1万人のユーザーをオーガニックで獲得しています。今後は全国への展開とグローバル市場や日本に移住した外国人にも利用してもらえるよう、多言語化サービスの展開を検討しています。
今後の検証では、地域のチラシ配信にも取り組み、リコーが持つ技術やコネクションやネットワークを活用してコンテンツを充実させ、事業成長を目指すと語り、発表を締めくくりました。
12.AIとXRを組み合わせた製造業向け製品検査システムの開発
株式会社Quark 風間 健人

冒頭、風間氏は株式会社Quarkについて以下のように説明しました。「Quarkは、AIと空間コンピューティングの融合によって、人々の視覚情報の最適化を目指す東京大学発のスタートアップです。メンバーの7割が修士課程以上の研究者であり、AIやXRに関する高い技術研究開発力を有しています。」
株式会社Quarkは、Apple Vision ProやQuest 3、Xrealなどの様々なデバイスにAIやXRを組み合わせることで、人々が「見たいものを自由に見える世界」を作ることを目指しています。今回のTRIBUS挑戦では、リコーと共に製造業における人手不足という課題に対し、自社の技術を活用して解決を目指します。溶接の市場は世界的に拡大傾向にあり、2030年には22.4兆円規模になると言われています。これに対して、AIとXRを組み合わせた製造業向けの製品検査システムという新しいアプローチで課題解決を図ろうとしています。検証段階では、技術的課題をリコーと共に解決し、最終的には製品化を目指します。また、その後は医療や教育など、製造業以外のユースケースも生み出していきたいと、さらなる展開を示唆しました。
13.「それ本物?」トレーディングカードのAI真贋鑑定サービス「VALUE SCOUTER SERVICE(VSS鑑定)」
株式会社コレクテスト 岩田 翼

岩田氏は、自身が5歳から様々なトレーディングカードを集めてきた経験や、さらに「神社仏閣カード」を全国60以上のお寺や神社と共にリリースした話を披露し、その偏愛ぶりで審査員の注目を集めながらピッチを開始しました。
現在、現代の美術品とも呼ばれるトレーディングカードはその人気が高まる一方で、市場には偽物が溢れ、様々な問題が生じています。株式会社コレクテストは、この課題に対し、トレーディングカードのAI真贋鑑定サービスを提供しています。このサービスでは、AIを使って高精度で真贋を鑑定し、鑑定証明書を添付しています。
トレーディングカードの価格は、真贋だけでなく商品の状態によっても大きく変動します。そこで、カードの状態を評価する「グレーディング」が重要な役割を果たします。「グレーディング」では、カードの状態を1から10までの10段階で評価し、例えばグレード1が12万円の商品でも、グレード10では5,000万円になるなど、価値が40倍近く変わることもあります。この状態評価は短時間で、かつ傷を見落とさずに公正に行われる必要があり、現時点では人の目で行われていますが、非常に緻密でありながらスピードも求められるこの作業には課題が多く、解決が求められています。
共創では、リコーや株式会社PFUの機械技術システムを活用し、グレーディング作業を自動化するシステムの開発を目指しています。最後に岩田氏は、「カードショップなどで働いている方々が目を凝らして行っている作業。この課題を解決したいと考えています。」と強調し、発表を締めくくりました。
講評
スタートアップ13社のうち、Investors Dayに進むのは次の9社です。
・株式会社THA
・株式会社ジョシュ
・株式会社エイチ
・EAGLYS株式会社
・株式会社 a.s.ist
・株式会社Circloop
・株式会社palan
・イオリア株式会社
・株式会社コレクテスト
社内外の審査員による講評で、株式会社リコー代表取締役会長の山下良則氏は参加企業に対して次のようにメッセージを送りました。

13社のうち9社になりましたが、様々な議論が白熱しました。4社の方々は、採択する、しないとかという問題ではなく、成長させてあげられるか、また、自社が成長できるかという掛け算のところで悩みました。決して4社の方々がレベルが低いので落選というわけではなく、我々自身が自己評価を行い、お役に立てない可能性を含めて選んでいます。TRIBUSは来年も続けます。何回も挑戦いただけますので、ぜひいろいろ視点を変えて挑戦してください。我々も、できるだけ公開情報は多くしていきたいと考えています。リコーって面白い会社だと思えば、ほかのスタートアップの方々にあそこは面白いぞと、なんといっても出るのはタダだからね、というぐらいの感覚で来ていただければと思います。9社の方々はこれから4ヶ月間、一緒に価値を向上するということで、この次はそこを目がけてカタリストも一緒につきますので、ぜひ一緒に進めていきたいと思います。どうもありがとうございました。
今回の統合ピッチを通過した社内5チーム、スタートアップ9社は、2025年2月7日までの間、リコーグループ内外からのサポートを受けながらそれぞれのアイデアのブラッシュアップや実証実験を行っていきます。またスタートアップ企業にはカタリストが伴走して活動を支援することになっています。
ぜひその結果をお見逃しなくご覧ください。
