カタリストは「自分が変わる」「会社を変える」きっかけになる
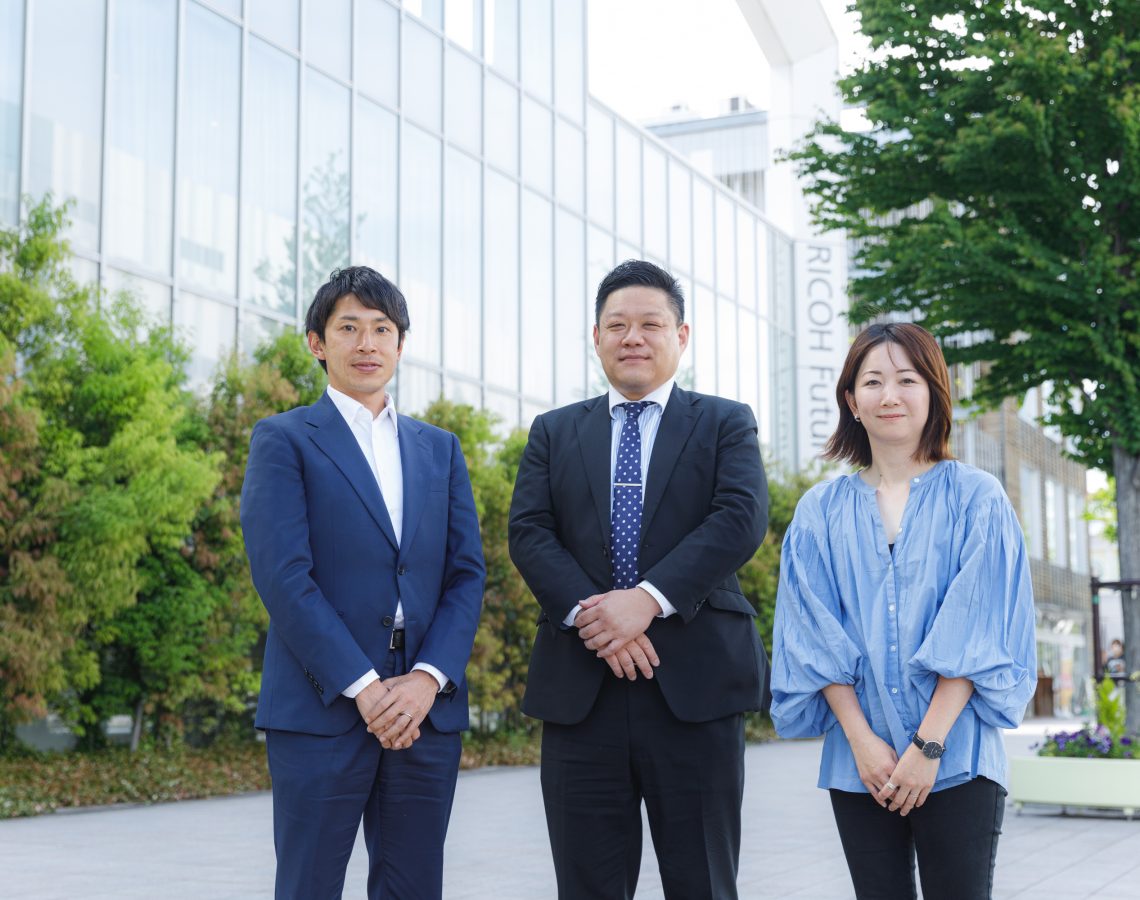
注目を集める社外のスタートアップ、社内起業チームはTRIBUSの「華」だが、スタートアップを裏側からサポートするカタリスト(※)もまた、なくてはならない存在であることは言うまでもない。むしろ、カタリストは多方面からの関りを余儀なくされるため、リコー社内における調整など表から見えるよりも大きな影響を社内に起こしているかもしれない。
また、自分なりにアプローチすることができ、自分なりの成果を出すことができるのもカタリストの面白さだ。この数年でカタリストとしてTRIBUSに参加した3名の話からは、そんなカタリストの姿が浮かび上がる。それは「華」ではないかもしれないが、誰もがなれる「たったひとつの花」なのだ。
※カタリストとはアクセラレーター期間にスタートアップ企業の伴走支援を行うリコー社員
生澤希
リコー未来デザインセンター TRIBUS推進室。2020年のTRIBUSにカタリストとして参加。当時はリコーデジタルプロダクツユニット所属で、MFP等の商品企画に従事。
松山智彦
リコージャパン デジタルサービス企画本部 PP事業部。2022年の統合カタリスト。当時は商品担当、現在は販売促進担当。
緑川瑠樹
リコーテクノロジーズ プロダクト事業本部 技術開発室。2023年にカタリストを務める。
――TRIBUSでカタリストとして関わるようになった経緯を教えて下さい。
生澤 2人目の育休明けで同じ部署に戻ってきたときに、気持ち的にはなにか新しいことをやりたいと感じていて、育休で離れている間に会社に変化はなかったかと調べていたら、目に入ってきたのがTRIBUSでした。自分が何か新しい事業を提案するにはまだ自信がなくて、社内と社外の橋渡し役であるカタリストなら自分の性質と合いそうかなと思ったんです。これまでのキャリアが活かせるポイントがあるかもしれないとも思いました。
 リコー未来デザインセンターTRIBUS推進室 生澤希
リコー未来デザインセンターTRIBUS推進室 生澤希
緑川 本業では新規事業開発をやっていまして、2019年のTRIBUSでは、イメージポインターの開発チームで採択されていたので、TRIBUS自体も、カタリストのことも知ってはいました。しかし、ゼロイチは得意じゃないと思っていたし、湯水の如くアイデアがボコボコ湧いてくるようなタイプでもないし、人と人をつなぐのは得意だったので、だったらカタリストなら行けそうかなと。流れも分かるので、自分の経験的にも良いかもしれないと思って手を挙げました。
 リコーテクノロジーズ プロダクト事業本部 技術開発室 緑川瑠樹
リコーテクノロジーズ プロダクト事業本部 技術開発室 緑川瑠樹
松山 当時、在職20年、転職も視野に今後のキャリアを考えていたタイミングだったんです。それで外に目が向いていて、リコーに所属しながら今まで以上に社外の人たちと関わることができて、これは美味しいなと思いまして(笑)、不純な動機かもしれませんが、視野を広げる目的でカタリストにエントリーしました。
また、業務でお世話になっていた先輩が、TRIBUSのこと、カタリストのことをちょうど教えてくれたんです。カタリストやってみなよと、背中を押して下さいました。それまで、情報は目にしていたかもしれないのですが、TRIBUSのことはまったく頭に入っていなかったんです。が、環境、タイミングと言うべきでしょうか。
 リコージャパンデジタルサービス企画本部 PP事業部 松山智彦
リコージャパンデジタルサービス企画本部 PP事業部 松山智彦
――担当することになったプロジェクトについて、どんな印象を持ちましたか。
生澤 ピッチを見た上で希望を事務局に出し、担当スタートアップが決まったのですが、With Midwife、KBEともに希望していたチームでした。With Midwife代表取締役の岸畑(聖月)さんはとにかくピッチが衝撃的でした。社会的意義があるという強い思いが、熱意などという言葉では言い表せないくらい感じられました。コロナ禍真っ只中でのアクセラ期間でしたが、担当することが決まったらすぐリアルで直接会いましょうと連絡をいただき、会ったらすぐ手を握って「支援してくださってありがとうございます!」と言ってくださいました。人と人のつながりを構築する力が非常に強い方だなと圧倒されました。
KBEは、人事的なサポートをされる事業という観点で個人的に興味がありました。代表取締役CEOの白壁(和彦)さんとはオンラインでMTGをしていましたが、少し会話をするだけでもその知性、実力の底知れなさを強く感じました。
松山 今カタリストとして応募したのですが、統合カタリストという、カタリストをサポートするカタリストとして活動することになりました。一歩下ったところから横断的に下支えするようなポジションで、前年にカタリストを横につなぐ機能がほしいという声があって、設置されたと聞いています。
統合カタリストとして、ScalarとSpread withを中心に、4社担当しました。外の空気という観点では、全部のチームのやり取りを見ることができたので面白かったなと思います。1対1のカタリストは、ともすれば入り込んで俯瞰的に見るのは難しくなりがち。より広く視野が持てたので、統合カタリストで良かったと思います。
緑川 スタートアップ1社につき、メインとサブの2人のカタリストが付くという体制で、私はオングリットホールディングスをメインで、RICOSをサブで担当しました。
RICOSはサブではありましたが、私がもともと開発業務の一環として流体解析に触れた経験があったことで、技術的にコメントさせていただく場面もありました。
またRICOSは流体解析シミュレーターのサービスで既に顧客も持っていて、リコー内でもヒアリングをしたいということで、社内のシミュレーション部隊につないだりしていました。社長の井原(遊)さんが実に切れ者で、会話していても話がダダダッと進んでいく。リコーの社員でありながら、スタートアップのそういうところを見られるのはカタリストの良いところだと思いました。
オングリットホールディングスがメインで、最初はなかなかスムーズにコミュニケーションがとりにくい印象がありました。九州の会社ですし、森川(春奈)社長が投資家回りをしたり、ビジコンに参加したりと忙しく活動されていて、なかなか直接お目にかかれなかったことも一因ではありました。

――具体的にどのような活動をされたのでしょうか。
生澤 With Midwifeは関西発の企業で、企業に顧問助産師を派遣するというサービスを展開しており、女性比率の高い、例えば金融系の企業を中心に数社で導入が進んでいました。岸畑さんは「顧問助産師が当たり前になって日本すべての企業に導入されるようになってほしい」という思いで活動されており、それに向けて、今のサービスをどういう方向に強化したら良いかを検証するのがアクセラ期間の狙いの1つでした。
リコーは男性の比率が女性より高い社員構成でWith Midwifeが当時あまりリーチできていなかった層です。新たな層にアプローチ可能だったこともあり、社員を対象にした実証実験を展開し、フィードバックを集めることに取り組みました。
KBEとは、アクセラ当初、リコーの各部署にサービスを展開しながら検証をすることと、リコージャパンの販路との連携を検討するという2つの狙いが設定しましたが、アクセラ期間の時間的な制約、という難しさもある中、アクセラ期間後も見据えてどう協業を進めるかというゴール設計を協議、調整していきました。
緑川 オングリットホールディングスは、インフラの点検を事業にしており、リコージャパンの営業車を使って、カメラ、AIでデータを取りたいということでした。主な対象はポール類で、直接点検が必要かどうかを判別する機能です。教師データの取得、取得データの解析の両方を同時に実証するということで、それができる環境づくり、準備を進めました。実際に福岡県の営業所で実施でき、営業車が非常に広い範囲で動いて、オングリットホールディングスの担当のかたも驚くぐらいのデータが取れました。
個人的には、提示いただいた撮影用のカメラの性能で本当にデータが取得できるのか、最初すごく不安で(笑)、技術屋目線でいろいろ尋ねてしまったんですよね。現地まで行き、実施にも立ち会って、ようやく納得しました。
RICOSはオーダーが比較的ライトで、社内ヒアリングしたいというものでした。どういう人が流体解析シミュレーションを使っているか、どういう困りごとがあるのか。どういう成果を期待しているものか。そして導入のハードルがあるとしたらそれは何か。複合機の排気、排熱や、機内でのトナーの動きも流体ですので、そういったシミュレーション部隊を紹介し、ヒアリングをしてもらいました。
松山 Scalar、spread withは、ともに製品・サービスがあり、リコー社内で実証実験をしたいという要望でした。統合カタリストとして、リコーグループ内で、顧客に近い場所、社員が多い場所で実証の準備を進めるところまで支援しました。こちらは、活動が本格化していくにつれて、担当者同士で動けるようになったので、その後は進捗を見守っていました。
統合カタリストとしての仕事は、一言でいえば、交通整理。担当カタリストから一歩引いたところで、少しブレーキを踏んだり、問題に対して対案を出したりといった役割でした。カタリストとはオンライン、対面両方でミーティングしていましたが、身内だけなので結構泥臭い、本音の話が出ていましたね。
TRIBUSに応募してくれるスタートアップにとっても、もちろんリコーにとっても、独自技術やノウハウは企業価値そのものであり、守られるべきです。その中で、技術やノウハウをどの程度共有しあうのか、腹の探り合いだけじゃなく、ぶっちゃけどうなのよ!と踏み込む口火を切る、流れを作るのも、統合カタリストの仕事だった気がします。
ただ、TRIBUSのあり方として、アクセラプログラム参加スタートアップとの関係性でリコーに短期的に利益を生み出すということを主目的にしていない、プログラム参加を関係性のスタートとして、お互いのメリットがまずはフィフティー・フィフティーでなくても良しとする風土があると理解していました。活動で議論が煮詰まった際の落とし所で、必ず我々がスタートアップさんに歩み寄り、何かお役に立てるポイントがないか探すというカードが用意されていたと思います。もちろん究極の長期的な目標として、リコーが会社としてTRIBUSに取り組んでいる以上、リコーに何らかのリターンがあるものにしなければならないとは思います。
しかし、それはTRIBUS全体のことであり、短期のアクセラ期間で伴走している間、スタートアップ1社1社に対して見返りを求めているわけではありません。そういうところがやりやすかったと思います。このマインドは、最初からカタリスト全員が共有していたというものでありませんが、スタートアップに一生懸命になる中で、また、プログラムにのめり込む過程で、TRIBUSの目標、意義、あり方、それらに自然と気づいていきました。
生澤 松山さんの今のお話ですが、統合カタリストの方がそういう視野を持ってくださっていることは、TRIBUS事務局の立場からするととてもありがたくて。アクセラ期間内に関係性を構築し、ゴールを引いて走り切るというのももちろん必要なのですが、アクセラが終わったらブツッと切れる関係性だけじゃないものを目指していきたいというTRIBUSとしての思いもあるんです。なので、横串を通している統合カタリストが、そういうスタンスでいてくれるのはすごく可能性を感じます。
――統合カタリストという役割は、最初から詳細な設計のもと設置されたポジションではないと聞いています。TRIBUSは、そのように「図らずもうまくいく」ということが多いようですが、それはなぜでしょうか。

生澤 私はTRIBUS事務局の所属になってまだ半年ですが、「自由に楽しくやる」というところがブレないからではないでしょうか。ガチガチに固めなくても、なんとなくポジティブな方向で予期しないことが生まれ、つながっていく。
事務局のメンバーは良い意味でゆるい面々ですし、とても自由です。普通、事務局という立ち位置の人の進め方は“ルールを守ってくださいね”と管理する方向になりがちだと思いますが、TRIBUSの場合はいい意味であまり介入せずに好きにやらせてくれる。カタリストになると、最初その自由さにちょっと戸惑う時期もあるのですが、後々振り返ると、それが良さだと気付かされる。だから、自分も事務局メンバーになって、ガチガチにしない、というところは大事にしていきたいと思っています。
緑川 生澤さんが仰ることはすごくポイントだと思います。私がカタリストをやろうと思ったのは、「こういう人たちが事務局をやってるんだ!」と感じ入ったからなんですよね。
仕組みじゃなくて人が先にある。それがTRIBUSの良いところじゃないでしょうか。多分、つまらない人たちがやっていると感じたら、私もカタリストに手を挙げなかったんじゃないかと思います。

―― カタリストでご苦労されたこと、逆にやりがいを感じたことは。
生澤 育休明けの年で、仕事と家庭の両立もまだままならない時期だったということもあり、本業とカタリストのバランスを取るのが大変ではありました。ただ、この点、カタリストがチーム体制だったので、他のカタリストメンバーと連携して、たくさん助けてもらいながらなんとか活動できました。実は、私はカタリストの経験はちょっと苦い思い出になっているんです。もっといろいろやれることがあったんじゃないか、という感想が強い。だからといって、やらなきゃ良かったということではなくて、こうすればよかった、こういうやり方もあった、とポジティブな気持ちの苦さです。
そんな中でも、With Midwifeチームの活動では、毎週2時間の熱い定例ミーティングを経て、実証実験の結果かなりのケース数が取れ、共同のリリース発表までアクセラ期間中に漕ぎつけた。苦しかったけど、お互いに熱く議論した甲斐があったと思います。
緑川 オングリットホールディングスは、先方の本気度を引き出すというか、信頼を得るというところで、一番苦労しました。会社の距離が離れていたこと、社長が忙しすぎて、なかなか直接連絡が取りにくかったことが一因であったかと。とは言えガチガチに進めたくはなかったので、社長が東京に来るタイミングで突撃して、実際に対面で話してみて、ようやくこちらの本気度が伝わって、向こうも、じゃあお願いしてみようかなと頼ってくれたり、こういうことをしましょう、という提案にも耳を傾けてくれたりして、徐々に近づいてつながっていくことができました。最後はこちらから福岡にお伺いするところまでいって、ようやく信頼が深まり、それ以降スムーズに進むようになった気がしています。
期間内にやりたいことがあるなら、少なくとも自分はそれを達成したいし、後悔しないレベルのことはやりたいと思ったんです。それで、リコーを利用してください、頼ってくださいというスタンスで臨んでいきました。最終的に福岡のリコージャパンで実証できたときには、ああ、実現したなと感慨深いものがありました。そこからが始まりではあったんですけどね(笑)。
松山 私は統合カタリストだったので、スタートアップとの付き合いよりも、カタリストとの付き合いに苦労しましたね。カタリストは基本的に担当するスタートアップについて口を出されたくない。だから、「こうしたほうが良い」というときには、そうは言わずに気づいてもらうように水を向ける。もどかしいようですが、それでこちらも気付かされることも多かった。これは、それまでの業務経験がいかされたと思います。何でも自分でやってしまうのではなく、交通整理、目標統合、そして周囲に動いてもらって大きな成果を出すこと、これを身にしみて思い知らされていたので、同じように対応しました。
また、一方で、矛盾するようですが、担い手がつかないタスクは、自分から率先して手足を動かすことも大切な点でした。そして、「この人に言えば何とかなるかもしれない」という立場を確立すること。頼っても良い存在だと認識してもらうこと。すると積極的に巻き込んでもらえる、頼ってもらえるようになりました。まさかTRIBUSで、人間関係を作るのにこんなに苦労するとは思わなかったのですが、他の統合カタリストも同じように言っていましたね。

――TRIBUSの可能性や、今後について期待することがあれば教えて下さい。
生澤 自分から手を挙げて入れるコミュニティということと、関わり方の選択肢が複数あるということは、TRIBUSの大きな特徴であり良さですし、リコーグループの社員なら、迷わず使った良いほうがチャンスだと思います。
カタリストに関しても、こういう人でなければできない、やっちゃダメというものでは全然なくて、語源となっている「触媒」の意味の通り、人と人をつないでその間で起こる化学反応を、ワクワクしながら楽しめる人なら、皆におすすめします。私のように、もっとできた、こうすればよかったという苦い思い出になることもあるかもしれません。
でも、それによって得られる気付きも多いです。社外の人たちのやり方、視座の高さや視野の広さ、日々どういう流れで仕事をしているか。そうしたことに触れるだけで、本業に対するスタンスも変わるし、新しいことをやろうという気持ちにもなります。ぜひ多くの方々にTRIBUSに関わってほしいと思います。
緑川 私だけじゃないと思いますが、TRIBUSのイメージってやはりピッチなんですよ。自らアイデアを出して、チームを作り、短い期間でアクセラレーションするというイメージだと思いますけど、TRIBUSはそれだけじゃないと私は思います。カタリストみたいな関わり方もあるし、協力してと頼まれてちょっと口を出すだけの関わり方もあるし、ウェビナーやイベントに顔を出して、こういう世界あるのね、と知るのもTRIBUS。何かしら気になる部分があれば、まずなにかやってみる、飛び込んでみる。それでいいと思います。
特にカタリストは、誰でもできるし、社内で初めて知ることが多くて面白かったです。社会インフラ事業の部署があることも知らなかったし、想像以上に幅広い部署があって、動けば誰かに当たる、必ずヒットするということも今回初めて分かりました。やっぱりまずは手を挙げて動いて見ると、ゼロからでも、知識、知見が増えていく。そういうために使っても良いんじゃないでしょうか。
松山 カタリストをやったことで改めてリコーグループは大きく、そこに、いろいろな人、いろいろな仕事があるのだと再認識させられました。技術の方や専門職の方、各ビジネスユニット……こんなにも無限に広がる世界の中で、自分は営業の世界しか知らなかったことに気付かされて、焦る一方で仕事に対するモチベーションが上がりました。
自分はしゃべりだけで生きてきた人間ですが、それでもTRIBUSに参加して自身の経験ですら活かされる場面がありました。様々なことが、TRIBUSの後も仕事の原動力になっています。転職のために応募したカタリストでしたが、逆にリコーグループでの仕事を続けるきっかけになったのは、結果としてうれしい誤算だったと思います。
PHOTOGRAPHS BY UKYO KOREEDA TEXT BY TOSHIYUKI TSUCHIYA
